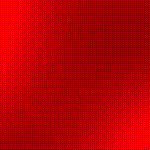いつもの森にある河原まで、フライアは戻ってきた。優雅に流れる河の水面は日の光でギラギラと眩しく輝いており、種類の判別しない魚たちが泳いでいる。分厚い装甲に守られた重い脚を動作させ、ズシンズシンと足音を立てた。奏汰にはそのことを気にする気力が残ってはいなかった。倒木がある所でフライアは立ち止まった。肩部と背部、そして脚部の排気口から蒸気を吹きだし、内部にたまった熱を放出した。
「ここまで来れば大丈夫だろ……」
「うん。近くに人も、敵影も無いし。多分、大丈夫かな」
「はあぁぁぁぁぁぁぁぁぁ」と大きなため息を漏らしながら奏汰は体重を背もたれに預けた。
正直、今回ばかりは生きた心地しなかった、と奏汰は先ほどの戦闘を思い返す。敵は飛行能力のあるロボットを投入しており、明らかな技術力の向上が見られた。一方でブースタのようなものをつけており、未だ粗い部分もあった。それでも、やはりフライアは戦車らしく対空戦闘には不利なのだ。いくらミサイルを搭載していたとしても、自由自在に空を飛ぶ敵には遅れをとってしまう。これをもし敵が知って、今後現れるロボットが全て飛行能力のあるタイプになんてされたら、どう対処していいか奏汰には分からなかった。考えるだけでも、厭な汗が流れる。
奏汰は、先程の戦闘で疲れていたし、精神的なダメージもあったので、それ以上考えることを放棄した。正直、もう家へと帰りたいと奏汰は思い始めており、ほんの少しコックピット内で休んだあと、座席を立ち上がって梯子を上り、ハッチを開いて外へと出た。
奏汰が胸元から出てくると、フライアは片手をコックピットの方へと動かし、彼の足場を作ってやった。
「さんきゅ」と奏汰はその手に飛び乗り、地面に降り立った。「はぁ、疲れたな。お疲れ様、フライア」
背伸びをして、奏汰は自身の疲労をアピールするかのように肩をグルグルとまわして振り向き、フライアに労いの言葉をかけた。
「うん、お疲れ様」
フライアは顔を下に向け、ロボットらしい単眼で彼を見つめる。応えるように、奏汰も見つめ返す。
ほんの一瞬だけ、友里の顔が思い浮かべられた。
あいつが造ったロボットなだけあって、本当に強いな。こんなものを造り上げてしまうあいつを、俺は…………。
フライアの純粋なロボットの顔を見つめて、そんな風に思っていると、ふと、パチパチという電気か何かの音が聞こえた。
視線を落とし、音のする方を確認すると、フライアの右脚部の鎧のようになっているカバーの下の装甲に穴が空いていた。普段装甲に守られているそこは、構造が分かるほどに内部が露出していた。人間でいう血管にも見えるコードが切断されている箇所があり、ここから火花が散っていたのだ。
「おい、怪我?破損?してるじゃんか」
心配そうな表情を浮かべ、奏汰が近づいた。それに反応し、フライアは右脚を下げ、彼から遠ざけた。
「これくらいなら大丈夫。今、自己修復プログラムを立ち上げたから、ちょっとすれば自然に直る。でも、人間には危ないから触らないで」
「自然に直るんだ…………」
「うん。だから心配しくていい。それより、奏汰の方は大丈夫なの?」
質問し返すフライアだが、奏汰はそんな彼女の質問よりも、破損した脚に関心があるようだった。間をあけて、ようやく彼は反応した。
「え?あ、ああ、俺は大丈夫だ。プロテクターのおかげかな。それよりもさ、あんま無理するなよ」
「誰かさんがもっと私を上手に操縦出来ればいいんだけど」
「う…………」
気にしていることを言われてしまった奏汰は、分が悪そうな表情でそっぽを向く。
「ま、そこはぼちぼちやるさ。それよりも、俺ら、2体も倒したんだぜ?すごくね?」
「凄いのは私の性能のおかげだと思う」
きっぱりと答えるフライア。彼女のこの発言に苦笑いを浮かべながら奏汰は頭をかいた。
「いやでもほら、俺も機転を利かしたというかなんというか……」
「それは、確かにそうだけど…………」
「だろ?」
「分かった、じゃあこの2つの戦いは私と奏汰、2人のおかげってことで」
「ああ、そうしてくれ」
奏汰は笑った。フライアは笑っているかは分からなかった。SF作品に出てくるアンドロイドと違って、純粋な戦闘兵器である彼女には表情はおろか、鼻も口もないのだから。
翌日、学校から親の電話宛てに臨時休校のお知らせメールが届いた。どうやら、先日のロボット騒ぎに加え、多発する事件を学校は危険視し、5日程度臨時休校を実施、及び生徒達には不要・不急の外出を禁止するという判断に至ったようだ。むしろここまで騒ぎになっても問題なく学校で授業が行われる方が、一般市民である保護者は怖いだろう。そういう訳で、奏汰、友樹、花蓮たちは自宅待機となり、暇を持て余していた。
「自宅待機って言ってもやることないよなぁ」
スマホ越しに、友樹は退屈そうな声を漏らした。奏汰はベッドに横になりながら、友樹のこの声を聞き流している。2人は休校期間でお互いにやることがなく、とりあえず電話してみることにしたのだ。ちょうど、電話での話題を2人は持っていた。
「しょうがないだろ。あんなのがあった後じゃさ…………。っていうか、俺がフレイアに乗って戦っている間、そっちどうだった?」
「おん?あぁ~」と友樹は昨日の事を思い出して唸った。「お前が行ったあとは大変だったな。学校中、もうパニックよ。先生たちが体育館に全校生徒集めて避難させたんだけどな、皆スマホ見ててさ。ネットに上がってるぞ、フライアと変なロボットが戦ってるところ」
「おう………マジか」
「ちょっと見てみろよ」
「ちょっと待って」
奏汰はスマホを耳から話すと、ボタンをタップしてスピーカーに切り替えた。そしてネット検索の検索エンジンに『ロボット 事件』と入力してみた。
「面白そうなことしてるね。私にも見せて!」
奏汰の背後から女の子の声がした。しかし、彼の部屋に女の子はいない。机の上には窓から入る陽の光に照らされた、あのペンダントが置いてあった。
「こういうのに興味あるのか?」
「知的好奇心は人間にだってあるものだよ」
ベッドから起き上がり、机まで歩くとペンダントを手に取った。
「ネットに繋がってないの?最先端のAIさんは」
「残念ながら、私にはこの世界のネットワークに接続する機能はないの」
「ないんだ」
青い結晶の部分をスマホの画面に向けながら、奏汰はスマホを片手で操作する。世界的に人気なSNSには様々な投稿がアップロードされていた。そのせいでトレンド入りを果たしており、ネット民たちがこの街のロボット騒動に関心を向けていることが分かった。奏汰は人差し指でスクロールし、それらに目を通してみた。
『これ撮影?リアルすぎ!』『爆発音したと思ったらなんかいたwwwwww』
『やばくない?』
『迷惑だわ』
『撮影?それとも本物?どちらにしろ迷惑すぎ!』『これは日本製だ(迫真)』『日本怖い……』
『ついにロボット兵器時代到来か』
『この黄緑色のやつ、前にも見たな。強いのか?』
『本物だとしたら凄すぎない?』
『戦争かと思った!』
『戦争反対!』
投稿の書き込みには動画も貼付されており、再生してみると30秒間の映像だった。画質の悪い映像には、不審な星型の物体が縦横無尽に飛ぶ姿と、それに対し攻撃を仕掛けるフライアの姿が映し出されていた。この投稿には1万いいねと400件のコメントがついており、『この映像は偽物だ』、『作り物じゃないのか』などのように懐疑的な声がある一方で『私も映像の場所に住んでいるんですけど、ガチでした。何回も爆発音してるし、怖くて怖くて、家に閉じこもってました』とその存在を認める声もあった。
「私たち、有名人なんだね」
「こんな嬉しくない有名人があってたまるか」
フライアの呑気な反応に奏汰はそうツッコむ。奏汰にとって気が滅入りそうなったのは2人に関する批判的な投稿。「こんな場所でなんでこんな事をするんだ」とか「子供を安心して外に出せない」という声が多かった。おまけに、フライアを悪者として捉え、犯罪者として扱うような内容まで投稿されている。
確かに、市街地での戦闘はまずかっただろう。奏汰やフライアからすれば、あれはロボットが暴れる事で生じる被害を抑えようとした善意のある戦いであった。しかし、戦闘中において、フライアが倒れたあの家にだって人が居たかもしれない。そして亡くなってしまったかもしれない。
助けようとした人々に自分たちを悪者のように扱われてしまうのは、どこかやりきれない。奏汰の心はどこか沈んでしまったような気がした。
「悪目立ち、してるな」
「だろ?」
はぁ、とため息をついて、俯いた。
「戦うにしても、もう少し気をつけないと、いずれフライアにいる森のことも突き止められるぞ」
「だよねぇ…………」
奏汰は悩んだ。
これからの活躍について。これからどう、戦っていこう?
沈黙が流れる。気まずい沈黙ではなかった。奏汰も友樹も真剣に考えた。これからどうするか。そんな2人の沈黙をフライアはただ黙って見ているしかない。風で揺れる窓の向こうからは、セミの鳴き声が聞こえた。沈黙を破ったのは友樹だった。
「なぁ、奏汰。会って、話そうぜ、あの河原集合でさ」
少し考える奏汰。それなりの付き合いをしている友樹の意図はなんとなくわかっている。このまま自宅待機していても拉致があかない。それにこんな大きな問題を1人で抱えるよりも、友達と会って共有したいと、心の奥底で、奏汰も感じていたのだ。
「分かった。いいよ」
自宅待機という学校の指示など気にも留めず、奏汰は身支度を整えると、ペンダントを首からさげ、靴を履いて家を出て行った。空は晴れていて、綺麗な青い空が迎えてくれた。奏汰はチラッと空を見た後、自宅の外に置いてある、少しチェーンが錆びついた自転車に跨り、ギアを3にして漕ぎだした。
日差しは熱く、薄っすらと汗ばんできた。金属音と風の音がついてきて、道を下っていく。狭い道、車通りの多い道路。右に曲がったり、左に曲がったりと匠にハンドルを操った。
通り過ぎるコンビニからは、老人が歩いて買い物袋を提げて出てきた。
それ以外に人や車はいなかった。普段は学校にいるから、ここらの通りがどうなっているかは分からなかったが、どこか寂しいものだと感じた。先日の戦闘により倒壊した家の前の道路は、アスファルトが割れており、通行止めになってしまっていた。仕方なく奏汰はUターンして迂回道路を使った。高校生特有の体力と、奏汰の持つ運動能力の高さにより、あっという間にいつもの河原へに到着した。