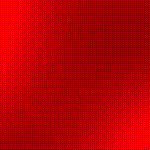ブラインドの隙間から陽の光が差し込み、目が覚めた。
薄っすらと、白い天井が目に入った。
「ここは……?」
僕は少し体を起き上がらせ、薄暗い部屋で、霧がかかったように安定しない頭の中をゆっくりと整理する。
そうか、ハンザの家に泊まってたんだっけ。
昨日のことを思い出しながら身の回りを見ると、隣でイオがすぅすぅと、気持ちよさそうに眠っている。
その姿に僕の心臓は大きく跳ねて、眠気が一気に吹っ飛んだ。
ドッキドキしている心臓を無視して、さっさと着替えようと、イオを起こさないようにそっとバックから服を取り出し、座りながら着替え始めた。
着替えに手こずりながらも、やっとズボンを履き替え終えたところで、イオが目を覚ました。
「ごしゅじんさま……?」
まだ眠いのか、イオは目を擦りながら体を起こした。
「おはよう。ブラインド開けていい?」
「はい~……大丈夫ですよ~」といつもは結構しっかりしているイオが、今だけは間の抜けた返事をした。
そのことを新鮮に感じながら、僕は立ち上がってブラインドを開けた。
「うわっ!」
ブラインドを開けた途端、陽の光が一気に差し込み、あまりに眩しさに目を瞑った。
「大丈夫ですか?」
「あ、うん、大丈夫。眩しくてビックリしちゃって」
「もう明るいですからね」
「うん」
そんなありきたりで、でもなんだかぎこちない会話をしていると、コンコンという軽いノックが聞こえた。
「おはよう、二人とも。もうすぐ朝ごはんにするよ」と、ハンザがドアから顔をひょっこりのぞかせて言った。
「分かった。今行くよ」
「ありがとうございます、ハンザさん」
ハンザに連れられて台所に行くと、すでにテーブルには朝ごはんが並べられている。
僕は、それが輝いて見えた。
家族の朝ごはん……か。
「あ!おはようございます慶介さん。イオさん!」
テーブルの端っこに座っているイシカが、元気で明るい挨拶する。
「おはよう、イシカ」
「おはようございます」
僕らも、清々しい気分で挨拶を返す。
僕とイオは昨日と同じように並んで椅子に座り、ハンザは僕の正面に座った。
「じゃ、全員そろったみたいだし、食べましょう」
ハンザのお母さんが、席に着いたところで、皆が食べ始める。
朝食は、何かのお肉や、紫色やピンク色の野菜っぽい食べ物が刻んであって、それにオレンジ色のソースがかかったサラダとや色とりどりのスープと、かなりシンプルな内容だ。
それでいて食べやすい味と歯ごたえで、いつもの朝なら中々ご飯を食べる気にならずちょっとずつ食べるところを、今日は料理をどんどん口に運んだ。
ふと、ハンザのお父さんがいないことに気づいたけど、その理由を訊くのは僕にとってはまだ難易度が高いし、知ったところでどうなるわけでもないから、僕は訊こうとしなかった。
「どうだった?ちゃんと寝れた?」とサラダを食べながら、ハンザは僕の顔を見る。
「あ、うん。結構寝れたよ」
夜、イオが淋しさや不安で中々眠れなかったのは言わなくてもいいだろうし、それに、あの後は本当によく眠れた。
「それで、今日はどうするの、慶介?」
「今日は、町の人とかに色々話を聞こうと思うよ」
「……どうしても、やる気?」
「うん、それが目的だからね」
「そっか。それなら俺も行くよ」
「え、でも……」
「いいよ。この近くの人なら顔見知りも多いし、俺の方がこの世界に詳しいからさ」
「……分かった」
僕達は、食べる速度を上げた。
朝食を食べ終え、歯を磨いて、ある程度の出掛ける支度をして、コスモスに頼んで装甲車を出してもらった。
「行ってくるよ、母さん」
「行ってらっしゃい。気をつけてね」
芝生が生え、小さな石ころが転がっている玄関の前で、ハンザの母さんは、ハンザにそう言うと、今度は僕の方を向いた。
「行ってらっしゃい、慶介君」
「はい、行ってきます」僕はお辞儀をした。
そして、装甲車の分厚い、小さな覗き窓のついたドアを開け、助手席に座った。
次にイオとハンザが後部座席に座り、ドアを閉めると、装甲車のハンドルとアクセルが自動で動いてゆっくりと走り出した。
イシカは友達と遊ぶ約束をしていたらしく、朝ごはんを食べて近所へ出掛けた。
あの子とも、もう少し仲良く出来たらいいのかな。
イオも、こんな僕じゃなくて、イシカみたいな同性の友達がいる方がいいのかな。
まだ舗装されていない、あぜ道のような凸凹した道をガタガタ揺れながら駆け抜ける装甲車の中で、そんなことを考えてみる。
友達というワードから凛音や里久の顔を連想し、その次に考えたのは、僕らを襲い、地球を壊した敵についてのことだった。
この世界で、この旅で何か情報を得られるのか、ハンザの言う通り僕のやろうとしていることは無謀なのではないのかという事だった。
「まずは、東の街へ向かおうか」
装甲車が分かれ道で停まると、ハンザは左の道を指さして言った。
「分かった。あ、えっと……装甲車、さん?左へ曲がって……?」と指示を出してみる。
装甲車は返事はしなかったけど、ハンドルが反時計回りに回り、左の道に進んでくれた。
道を進んでいく途中で、急に舗装された道路に入り、揺れは大分なくなり、音も静かになった。
装甲車は窓がものすごく小さいため、視界があまり良くなく、周りを確認するために台の上に乗ってハッチから上半身を出した。
畑や、小屋の数々が遠いものはゆっくりと、近いものは早く流れていった。
風の音以外は、とても静かに感じた。
誰か人がいないか、風景を眺めながら探していると、前方の道の端っこに歩いてる男女二人の人影が見えた。
「装甲車さん、ちょっと停めて」としゃがんでお願いをすると、装甲車は徐々に減速してその二人の隣に停まった。
女の人は細く色白で、身長は僕より背が高く、その隣を歩く男の人の方は少し日に焼けていて、がたいがよく高身長だった。
男の人が簡易的な日よけを取り付けられた小麦色の乳母車を押していて、その中には白い布でくるまれた赤ちゃんがいた。
多分、家族なんだと思う。
僕らが車を降りて、二人に声をかけようとした。
すると、男の方がハンザを見つけ歩み寄った。
「おや、ハンザじゃないか」
「あら、こんにちは」
「あ!こんにちは」ハンザはお辞儀をした。
どうやら知り合いらしい。
「ハンザの友達かい?この辺じゃ見ないが……。それに見たことない乗り物に乗っているな」
「僕は慶介、この子はイオです」
僕とイオもお辞儀をした。
「二人は異世界の友達です。旅をしていて」
ハンザは僕らの一歩前に出て言った。
「そうか異世界の友達か!いい事だな。旅をするには若すぎる気がするが」
男の人は、心地よいほど勇ましく笑った。
「今日は、訊きたいことがあって……」
「何かしら?」
今度は女の人が澄んた声で応えた。
「その……白くて、巨体で、武装をしている船や、それを扱う世界を知りませんか?」
「白い船を扱うやつはいくらでもいる。それだけじゃ分からないな」
「えっと、じゃあ他の世界を壊そうとしている危険な世界はありますか?」
二人は顔を見合わせた。
「すまない。知らないな」
「その船がどうかしたの?武装しているって言ってたけど……」
「その船を扱ってる世界に、僕は行きたくて……。それで旅をしているんです」無意識に、僕は視線をそらした。
「そう……他の人なら知っているかもしれないけれど。それでハンザ君は案内をしているのね?」
「はい」
「僕らは、そろそろ失礼します。ありがとうございました」お辞儀をしながら僕は言った。
「そうか!良い旅を、な」
僕はもう一度お辞儀をした。
「イオ、行くよ。……イオ?」
「ご主人様。この小さな子は、もしかして赤ちゃんですか?」
イオは赤ちゃんをじっと見つめていて、赤ちゃんはそんなことは気にせず笑っている。
そういえば、彼女は赤ちゃんを間近で見るのは初めてだったかもしれない。
さっきから気になっていたようだ。
「さ、触ってもいいですか?」
「ええ、いいわよ」
イオがそっと人差し指を赤ちゃんに近づけると、赤ちゃんはその小さな手で指を握った。
赤ちゃんは声を出して笑った
それを見たイオは指を握らせたまま、そっと柔らかく微笑んだ。
こんな笑顔は初めてだった。
その後も何人かに尋ねてみたけど、特に収穫があるわけでもなく、車で移動することに疲れてしまった僕らは、ハンザの家からかなり離れた丘の上の木陰で休憩することにした。
この丘をちょっと下ると、家やお店が密集していて、比較的人が多い街だ。
イオは、何かに惹かれているかのように、ちょっと半れた茂みまで歩いていて、僕とハンザはそれを眺めながら地面に座っている。
「慶介はさ、人と話すのが苦手?」
「苦手……なのかな。同級生とか、先輩ならまともに話せるのに、大人はどうしてもかしこまっちゃってさ。……でも話すのは好きだし、知らない人とでも話せるから、よく分からないよ」
「ふぅーん。そうか。俺は、この辺の人となら大体顔見知りだしなあ。それこそ大人と話すのだって多いから、そんな感じになった事ないな」
僕からすればとてもじゃないけど真似できないようなことを、ハンザは平然と言う。
「ハンザは、凄いね。僕と変わらない年齢なのに、自分で次元航行船(ふね)を操縦できるなんて」
「慶介だって、コスモスがいるじゃないか。高性能の」
「全自動だから、特に何もやってないよ。本当は、何か出来たらいいんだけど。いつも助けられてばっかで……」
「どれだけ船が優れていても、結局は乗る人間次第でその船の運命も自分の運命も決まるって小さい頃から父さんに言われたっけな」
無意識に、僕は下を向いた。
「でも…」とハンザは続ける。
「これからなんじゃないかな?君にはイオがいる。コスモスも、機械的だけど意思がある。最初から歩ける人間なんていないんだから、一緒に旅をしていくうちに覚えればいいって、俺はそう思うよ」
そう言いながら、ハンザは立ち上がった。
「……ありがとう」
なんだか少しだけ、肩にかかっていた重い何かが、頭にかかっていた暗い雲みたいなものが晴れたようながした。
ここで吸う空気が、僕の気持ちをそっと持ち上げてくれるような感覚になった。
「じゃあ、訊きに行くの続けようか」僕もハンザの横に立ち上がった。
「よし、行こう」
そう里久が答え、二人で背伸びをした時だった。
何かの鳴き声が聞こえ、小鳥の大群が一気に飛び立ったかと思うと、今度は山の方から大きく悪趣味な模様が施された、クジラのようなゴツゴツした形の船が一隻、飛行して街の方に接近している。
視線を落とすと、離れたところにいたイオが小走りでこっちに来ているのに気づいた。
「ご主人様、あれは、あれは何でしょう?」
「僕には分からないけど……。とりあえず街へ行こう」
僕らは、一旦装甲車に乗り、その船を追うために丘を降りた。