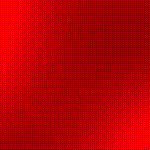街に引き返してみると、崩壊した建物のから少し離れたところにさっきまでは無かった黄色い船が停泊していた。ハンザ曰く救護用の船らしい。
コスモスから降りてみると、緑色の服やズボンを身に着けた救急隊らしい人達が、慌ただしく瓦礫だらけになった道を駆け回っていて、血まみれになって倒れた人を拭く数人で運んだりしていた。
僕とハンザ、イオは並んでただ呆然と立ち尽くしていた。
「船の数が足りねぇ……。このままじゃここに居る全員を運ぶのは無理だ……」近くにいた救急隊の一人が呟いた。
多くの船や隊員がここに集まっているけれど、それでも足りないのだ。
今の僕に出来る事……迷ってる余裕はない。そのためにここに戻ってきたのだから。
「あの!すいません!」僕はその人に思い切って声をかけた。
「君は……?誰か怪我しているのか!?」と振り向き、笑ったことなんて無いような真剣な表情で言った。
「あの、よければ僕の船を使ってください!」
「君の船?」
「あれです!」コスモスを指さした。
「あれが君の船か?異様に大きい、というより長いが……」
「お願いします」
「いや、しかし……」
目を泳がせて、曖昧な返事を返した。
「たしか、事件や事故が発生した場合、可能なら近くの船が救助するのが義務のはずです」ハンザが横から言った。
「それは異世界間の超空間の話で……って気にしている場合じゃないか。君の船には医療用の道具か何かあるか?」
「医務室があります」隣からイオが答えた。
「分かった。軽傷者の輸送を頼む。隊員も何名か同乗させてもらう。ある程度収容出来たら、アルフヘイム中央病院へ向かってくれ」
「分かりました!イオ、近くの軽傷者をコスモスに誘導して。ハンザと僕はちょっと離れたところまで、負傷者がいないか探そう」
「はい!ご主人様」イオはすぐに周りにいる人たちのもとへ走っていった。
「僕はコスモスに事情を話してくるから、ハンザは先に行ってて」
「分かった」
そう言って走っていくハンザの後ろ姿を少し見送ると、僕は走ってコスモスの所まで戻った。
道中、ボロボロの姿で倒れている人とその手を握って泣いている人が目に入った。
まだ小さい子供の、母親を求め泣き叫ぶ声が心に刺さる。
「本当に酷いな……どうしてこんな事に……」
コスモスの客車、二号車へ駆け込み大声で命令した。
「コスモス!!負傷者を乗せるから、受け入れる準備して!」
「了解しました。準備します」
全車両の乗降口を開いた。
コスモスは僕の命令に従って、皆を助けようとしてくれているんだ。
「よし!とにかく皆をコスモスに運ばなきゃ!!」
それから皆で手分けして、隊員の指示に従いながら道端に倒れている人たちに声をかけ、待機しているコスモスに誘導した。
僕とそう年の変わらない男の子や、細く長身のお兄さん、倒れていたお姉さん、膝を怪我した老人と、誰もが怪我をしている人たちを出来るだけ急いで、でも落ちついて、ときどき肩を貸したり背中に担いだりして着々とコスモスに誘導した。
医務室だけでは人が入りきらないので、客車のボックスシートや食堂車、客室、僕の部屋に至るまで、負傷者の収容に使った。救護班も何人か乗り込み、負傷者の手当てをしている。
さすがに起き上がることのできない程の大怪我をしたお爺さんは、僕にはどうすることも出来ず、隊員が持ってきた担架のようなものに運ばれていった。
しばらくそれを繰り返した後に外を走り回って、もっと他に手伝えそうなことを探した。
崩壊した建物の下敷きになってしまった人もいるようで、隊員の何人かが大きめの機械を手に持っている。
「あ!慶介」ハンザと合流した。
別々に行動していたのはほんの少しの間だったけれど、僕もハンザもかなり泥や塵で汚れていた。
「そっちに人は?」
「あらかた船に乗ったよ。ほら、あれ」
ハンザの指さす方を向くと、重症の人を乗せた救急隊の船が次々に離陸していく。
「じゃあ、コスモスも……」
そう言いかけた、その時だった。
「瓦礫の下敷きになっている人がいるぞ!」と誰かが叫んだ。
僕とハンザが走ってそこに向かうと、人の体の何倍もの大きさの瓦礫の下から女性の上半身が出ていて、小さな女の子がその人の手を引っ張ってる。
「ママ!ママ!」女の子は叫んだ。
その子の母親はかなり疲弊している様子だった。
周りには血まみれの男の人たちが数人いて、瓦礫を持ち上げようと協力していた。
僕とハンザもそれに加わる。
「いくぞ!せーの!」
誰かの声で僕らは一気に持ち上げようとするが、瓦礫は一向に動く気配がない。
早く助けないと!思って周りを見たが、隊員たちは別の場所で救助活動を続けていてこっちには来れそうになかった。
「ご主人様!」
イオが僕の方に駆け寄ってきた。
「何かあったんですか?」
「下敷きになっている人がいて……」
イオは、下敷きになっている母親、そしてその腕を掴んで泣いている女の子を交互に見た。
「……ご主人様、私に命令してください」
「!?こんな時に何を言って……」
「お願いします」
その表情は真剣そのものだった。
「……この人を助けて、イオ!」
「かしこまりました。皆さん下がってください」イオの緑色の瞳は紅く染まった。
「何言ってるんだお前だけじゃ……」
タンクトップ姿の男の人がそう抗議しようとすると、イオは無言で男を睨みつけた。男の人はそれ以上口を開かなかった。
僕らは瓦礫から離れ、今度はイオがゆっくりと瓦礫の下の方を掴んだ。
そして数人の男でもびくともしなかった瓦礫を、イオはたった一人で持ち上げてしまったのだ。まるで瓦礫に似せた軽い素材でできたセットを持ち上げるかのように、軽々と。
周りにいた人たちは驚きで開いた口がふさがらない、という様子だった。
「ママ!」女の子は泣きながら母親に抱きついた。
「大丈夫ですか!?」隊員の一人が来た。
僕らは状況を説明して、隊員にその親子を引き渡した。
それを見守っていると、今度は別の方から叫ぶ声が聞こえた。
全身がボロボロの若い女性が崩れかかっている建物に向かって誰か人名を叫び近づこうとしていて、二人の男がそれを止めている。
「どうしたんですか?」
僕はその人たちに話を聞こうと近寄った。
「ヒロ君が…ヒロ君があそこにいるの!」
女性は指をさして、泣き叫んだ。
「あんたが行ったら危ない!今救助隊が助けに行ってるから!」
二人の男のうち片方がそう言って説得しようとしているがかなり混乱しているのか、聞く耳に持たないといった感じだ。ヒロという人がいる建物近くに隊員たちが集まり合図を出していて、機械を運んでいる。どうやらいるのは確実らしい。
しかし、建物の破壊のされ方はかなり複雑なようで、正直かなり手こずっている。何よりもうすぐで崩れそうなのだ。
僕の中で迷いが生まれた。今すぐ走って、助けに行きたい。でも何もできない。そうkンが得ている間にも、建物は音を立てて崩れている。
「……イオ、あの建物に取り残されている人たちを救出できる?」
「お任せください、ご主人様」
「あ!こら!」
男の人の制止も聞かず、イオは建物めがけて走っていき、三階の窓へ飛んで入ってしまった。
今はイオを信じるしかない、そう考えながらも不安でたった一分のことが酷く長く感じた。
一分も立たないうちに、イオは男性を抱えて窓から飛び降りた。
「ヒロ君!!」
ヒロと呼ばれる男性はイオの腕から降りると、走ってきた女性を抱きしめた。
「ご主人様、中にまだ人がます」
「分かった!その人たちも助けてきて」
「はい!」
イオは建物からさっきと同様に五人ほど運び出すことに成功し、これで全員だと言った。その直後、建物は完全に崩れてしまった。
隊員に引き渡したあと、イオの瞳はすっと綺麗な緑色に戻った。
「ご主人様、この辺の人はこれで大方救助し終えました」
「あ、あぁ。うん、ありがとう」
僕は、土まみれになったイオの服を軽くはたいた。
「凄いね、イオは」と隣にいたハンザが言った。
口は笑っているけど、目はまだ驚いている様だった
正直、僕もここまで身体能力が高いとは知らなかった。
いや、家の屋根から屋根まで飛べるなら、これは当たり前のことかもしれない。
「そろそろコスモスを出さなきゃいけないから、行こ」
「あ、うん……」
「分かりました!」
「あの、よろしければ僕の船で病院まで運びます」僕は、近くにいた軽傷の男の人たちに近づいて言った。
「おう、助かる」背が高くて筋肉質な人が答えた。
僕はイオと並んで歩き、その後ろに皆がついてきていた。
時々後ろを振り向いてみると、筋肉質の男の人以外がイオを横目で見ていて、それはコスモスに着くまで続いていた。
コスモスに戻ると、車内では隊員たち数名が負傷者に包帯をまいたり消毒したりして傷の手当てをしている。
どの車両も怪我をした人で一杯で、人の声が重なり合いそれ以外の音は耳に入って来なかった。
僕はとりあえず、身振り手振りで男の人たちを客車の隅の席に案内した。
コスモスに大勢の人が乗るという、普段見慣れない光景を目の当たりにして、僕はなんだか少し落ち着かなかった。
「それじゃあ、そろそろ行こう、コスモス」僕は客車から命令した。
「了解しました。圧縮機関圧力上昇完了。同調率84%。防御系統、走行系統異常なし」
「コスモス、アルフヘイム中央病院へ向かって発車」
「了解しました。発車します、ご注意ください」
それまでの車内の騒音をかき消すような迫力のある長い汽笛の声がして、それまで騒いでいた人達は急に静かになった。
窓の外を見るとゆっくりと動き出していて、加速しながら段々と空中を上っていった。
席は全部人で埋め尽くされていて、僕は通路の真ん中をうろうろ歩いてまわった。
客車では負傷者たちはうつむいていて、微かに誰かのすすり泣く声が聞こえた。皆、疲弊しきっていた。
しかしそんな中でも元気な人はいるもので、床を足で思いっきり踏みつけながら、不平不満を叫ぶ者もいた。
「なんで自分がこんな目に遭わなければいけないのか」と。
きっとそれは、誰もが思っているんだと思う。
そんな中、ふと近くで話している二人の男の声が耳に入り、僕はその会話の内容に耳を傾けた。
小声だからこそ余計に聞こえて、その会話の内容がイオのことについてだったからだ。
「あの子だあの子。あの白髪の女の子だ。あれが一人で数人がかりの男でも無理だった大きな瓦礫を持ち上げたんだってよ」
「まさか。そんなことあるわけないだろ。どう見たってそんな事なんて出来なさそうなくらい細いぞ」
「いやでも見たってやつは多くいるし、実際に近くにいた奴だっている」
「それじゃあ、お前はあの少女が人の皮を被った化け物だとでもいうのか?怪力の」
「そうとしか考えられないだろ。人間技じゃねぇ」
「けどな、やっぱり信じられんよな」
「……実は俺は不安なんだよ、この船に乗るの。この船、あの少女のなんだろ?」
「化け物の乗る船ってか」
イオの方に視線を向けると彼女は今車両の反対側にしゃがんでいて、腕に包帯を巻いている小さな女の子と話をしていた。
確かあの女の子はさっきまで泣いていたはずだけど、今では二人とも明るい笑顔を浮かべていた。
きっとイオが元気づけてくれたんだろうな。
この距離なら多分聞こえてはいないと思うけれど、僕としてはこんな話をされてなんだかが悪くなった。
何か言い返そうかと迷った。
そこにハンザが二人の男の間に割って入った。
「おじさんたち、この船は大丈夫だよ」
「あ、お前ハンザか!お前も乗ってたの?」
「まあ、そうだね」
「ひでぇ目に遇ったもんだな」
「まったくだよ」
ハンザは笑いながら、僕に散らっと視線を送った。
「ハンザ、僕は前の車両に行ってるよ」
「ああ、行ってらっしゃい」
僕は人と人の間をすり抜け、客車を後にした。
後ろから「え、今のがこの船の持ち主なの?」という声を最後に、あのおじさんたちの会話は聞こえなくなった。
指令室で僕は中央のモニターを見る。
「コスモス、あとどれくらいで着く?」
「約25分です」
「それまで、僕は何もしなくていいのかな」
「マスターはさっき外を走り回っていたのでお疲れのはずです。今はゆっくりお休みください。お茶を用意しましょうか?」
「いや、お茶はいいや。ありがとう。そうだね…少し話そうよ」
近くの椅子に座った。
「かしこまりました」
「あのさコスモス、もしも装甲車じゃなくて君に乗って来ていたら誰も亡くならないで済んだのかな」
「その可能性は高いですが、市街地で交戦状態となりますと、それだけ被害が大きくなったかもしれません」
「そっか……」
僕はうつむいた。
「そういえば、何であの時来てくれたの?」
「装甲車を通じてマスターの危険を検知し、自動防衛装置が働いたためです」
「あ、装甲車配収し忘れてた」
「救助活動中に回収しておきました」
優秀……!
「結局、あいつらの目的は何だったんだろうね。何でいきなり街に……」
「分からない事だらけですね」
本当に分からないことだらけだ、そう思いながら外の青い空を映してるモニターを横目で見ながら、深くため息をついた。
背もたれに寄り掛かると、今まで気づかなかった疲れを感じ、一気に力が抜けていった。
「……今日も助けてくれてありがとう、コスモス」
「そのための私ですから」
「皆を病院で降ろしたら、すぐにハンザの家に戻って休もう」
「了解しました」
負傷者を無事病院へ運び終え、駆け付けた警察に事情を説明した。
僕たちがハンザの家へ帰ったのは、日が沈んでからだった。