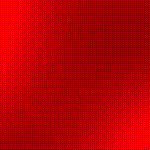奏汰と友里は見つめ合った。
片方は困惑の表情、もう片方は覚悟を決めた表情。
先ほどまで2人きりで静かだったはずのラボには、危険を知らせる警報が鳴り響いている。それは壁に掛けてある時計が、チッチッチッと秒針を鳴らし「時間が無い!急げ!」と必死に伝えようとしているのに、その音すらかき消してしまう。
実際、2人には猶予は残されていなかった。こうしている間にも武装した男たちは家の周りに静かに囲い込み、突入の機会を伺っている。
「奏汰、こっち!」
友里は手を引いて、玄関とは反対の方向へ走った。
「なぁ、あいつら一体何!?何で友里の家に来てるんだ?!」
「ごめん。ごめん。本当にごめん。巻き込んでごめん」
訳も分からないまま走る奏汰と、何故か謝罪する友里。
玄関が蹴破られる音がした。
窓ガラスに人の影があった。
その影は、銃の柄の部分で窓を割ろうと叩きつけた。
瞬間、窓は電気を帯び、ビリビリと電線がショートしたような音がした。
友里が仕掛けた防犯システム。
彼女が言っていたのはこれか、と奏汰は察知した。
家の近くに不審な人物を知らせる装置に、簡単には侵入させない仕掛けが施されていた。
ここで疑問に思うことは、何故彼らがただの女子高校生を狙うのか、何故彼女はそれを察知出来たのかという事。
何故、どうして、そんな疑問ばかりが奏汰の頭の中で渦となった。
目の前に危険が迫っていることは明白だった。
急ピッチで増設した防犯システム。
何とか機能してくれたという程度で、空き巣や強盗など比較にならないほどの手練れたちを相手に出来るほど完璧ではなかった。
2人が向かった先は、人が3、4人は入れるほどのほんの少し大き目のクローゼット。
ここに隠れるのか?と思っても不思議ではなかったが、友里は天井に引っ掛けてある紐を引いた。
すると紐が引かれたことに反応して、天井が落ちてきて、階段が現れた。
「これって、2階へ上がる?」
「そう。ここから逃げる」
「逃げるって言って、2階からじゃ無理だろ」
「大丈夫。お願いついて来て。このままじゃ2人とも危ない」
真剣な表情で奏汰を見つめる友里。
そんな彼女を見つめ返す奏汰。
およそ10秒の間、2人は見つめ合った。
幼い頃から一緒に遊び、共に過ごし、誰よりも近くで見てきた女の子を、ずっと思いを寄せてきた人を信じようと奏汰の中でこの時、ある程度決心した。
まだ状況は掴めないが、とにかく今は武装した男どもから逃げ、安全を確保するしかない。
奏汰と友里、2人が階段を駆け上がると、そこには不自然な空間があり、窓は設置されているというのに肝心のその空間に入るためのドアはない。
つまり、この空間に入る手段がクローゼットの中にあった隠し階段だけでなのである。
「どうするつもりなんだ?」
友里の方を見ると、彼女は何やらペンダントらしきものを握っている。
菱形の小さく平べったい板の真ん中に、青いクリスタルガラスのようなものが装飾として施されている。そしてその板の端の方を銀色のチェーンで繋ぎ、首からかけている。
それは彼女がずっと身に着けてきたモノである。
小さい頃はそんな物は身に着けていなかったというのに、いつの間にか身に着けていたのだ。
お洒落に興味があるような性格でもないにも関わらずである。
「奏汰……ごめんね。」友里は縋るような眼で奏汰を見ると、次に瞳を伏せ、そのペンダントにキスをした。それからまるで水でも掬うかのように、両手をお皿の形にして、掌に置いた。
「私たちを助けて!」
すると、友里の叫ぶ声に反応してペンダントが輝きだした。
不思議なことに「セットアップ」と機械的な声が、何の仕掛けもないはずのペンダントから発せられた。
実は、このペンダントこそが友里の開発した傑作のひとつなのだ。
「奏汰、飛んで!」
「は!?」
窓ガラスを開き、レールに足をかけて奏汰にこの窓から飛び降りろと、そう言うのである。
ここは2階、当然こんな所から降りれば怪我は間違いない。よく空挺部隊であるような五点着地を用いれば安全に着地出来るだろうが、しかし奏汰も当然友里もそんな訓練など一度もしたことが無かった。
とはいえ、このままグズグズしていてもいつかは発見される。覚悟を決めたじゃないかと、奏汰は自らを鼓舞し、友里と手を繋いで窓から飛び降りた。
同時に友里の家が揺れた。
地震や爆発ではない。家全体が揺れるというよりかは『何か』大きなものが動き、その衝撃で揺れたのだ。
その何かは、壁を突き破り、飛び降りた2人を空中で器用にキャッチした。
窓に設置されていたガラスも同時に割れ、月あかりでキラキラと反射しながら、ポタポタポタと細かい破片となって地面に落ちた。
「うわ!!」
「きゃ!」
奏汰と友里はというと、地面へ落ちることなく、何か金属に包まれたような感覚がした。
それは2階から地面までの距離よりずっと短かった。
その金属の物体は、2人を抱きかかえると、風を切って走り出した。
「ね、ねぇ、これは一体どういう事だよ………」
「この子、やっと機動できた。成功、したんだ」
ますます混迷する奏汰に対して、友里は達成感に満ち溢れた表情をしていた。
「頼みから説明してくれって」
奏汰が友里に身を寄せようとした瞬間、カン!カン!と金属の板を叩くような音がした。
身動きが上手く取れない奏汰は、身体をよじらせて金属の塊の影からちらっと後ろを確認すると、遠くの方で閃光が炸裂している。
またカン!と何かを弾くような音がした。
よく目を凝らして見ると、彼らの周辺で閃光が光った直後に音が鳴っている。
「これ………撃たれてる?!」
なんと、武装した男たちが、2人が逃走したことに気がつき発砲しているのである。
その弾は金属の板によって弾かれている。
しかも驚いたことのにこの『何か』2人を抱えながら水平に移動しているのだ。
友里の家はみるみるうちに小さくなっていく。
外はもう暗い。
道に沿って並べられた街灯の明かりと家々の生活の光だけがこの暗闇を照らしている。
車通りを出来るだけさけ、八百屋さんのある角を左へ、24時間営業しているコンビニエンスストアを右へ、とにかく追いつかれないようにあちこちの角を曲がったちしなが、ひたすら逃げた。
ただし、ずっと逃げていても巻けないため、結局は河川敷にかかった鉄道の鉄橋の下に『何か』と一緒に隠れた。
『何か』からおり、柔らかい土に足をつけた。
靴は履いておらず靴下だけのため、小石が突き刺さった。
痛いことには痛いし、普段であれば小石を払うくらいのことはしていただろうが、今はそんな余裕は無かった。
「説明、してよ。何で襲われたんだ?これは何だよ?」
奏汰は物凄い剣幕で、今にも襲い掛かりそうな勢いで問い詰めた。
それに対し、友里は目を反らし、ゆっくりと応えた。
「この子は、タイプI-903……フライア………。私が作った、思考人型機動戦車。自分で考える戦闘ロボットだよ」
奏汰はフライアと呼ばれるそれを見上げた。
しかしここは街灯もない暗い鉄橋の下。
ただの暗い影にしか見えなかった。
友里のもつペンダントが小型の照明のように光り輝いているおかげで、彼女の姿は見えたが。
「ロボットってどういうことだよ……。それじゃあ、工場を襲ったのって………!」
「違う!私じゃない!この子じゃない!私たちは関係ないの!」
首を振り、全力をもって否定する友里。
彼女の声、言葉、動きからその必死さと誠実さが伝わっている。
嘘をついていないことは奏汰にも分かった。
友里は、一度深呼吸をして、間を置いた。
そしてゆっくりと、口を開いた。
「聞いて………奏汰。本当は、隠していたことがあるの。信じて貰えないと思うけれど………」
そう話しを切り出した彼女の手と足は、ガタガタと震えていた。
これから話すことを聴けば、奏汰は自分を軽蔑し、嫌い、信じてくれなくなると分かっているからだ。
「聞くよ。何だって受け止めてやる。だから、話してみてくれ」
真っすぐと彼女の瞳を見るめる奏汰。
コクンと頷き、友里は話を続ける。
「本当はね、私、前世の記憶が、あるんだ」
「……………は?」
奏汰は自分の耳を疑った。前世の記憶。それはSFか、はたまた異世界転生系の小説でありがちな設定だった。友里の口から信じられない真実が告げられたのだ。そんなことがあるはずがない。
奏汰は疑いの目を彼女に向けながらも、最後まで話を聞こうと、喉まで出かかった言葉を飲み込んだ。
彼女は続けた。奏汰と出会う前の物語を。
本物の科学者としての生涯を。
彼女の前世は、地球よりもずっとずっと発達した世界の化学者でった。名前も『小黒友里』ではなかった。
『ヴァ―レ・リーベ』
それが彼女の前の名前であった。この頃から白衣を常時着ており、周りから変人扱いされていたのと同時に尊敬の念も抱かれていた。彼女は、当時からこの世界でも優秀な分類に入る科学者で、軍事産業の開発を行っていた。
また、空を飛び、異世界へ行く列車だの、巨大な空中戦艦だのにも携わってきた。
その世界でも兵器の開発に関して言えば、彼女は天才だった。
彼女は今では信じられないほど周りの人間と積極的に関わろうとしてきた。上司にも同僚にも部下にも好かれていた。コミュニケーション能力というのは、実は研究者にとって欠かせないものだったのだ。1人で何かを成し遂げることなどできない。
そんな彼女が何よりも熱中したものは、新しい兵器の開発だった。
兵器をと言っても、大量に人間や物を殺戮することを好んでいたわけではなかった。
むしろ平和利用、戦争の抑止力として使えるのではないかと考えていたのだ。
そんな理由から思考人型機動戦車I-903『フライア』が開発されいたのだ。
見た目は人型のロボットであるが、二足歩行用の脚部にはキャタピラを備え、機関砲や主砲を武装とする地上最強の兵器の実験機である。
フライアの完成間近に、不幸かそれとも誰かに仕組まれたのか建造用の資材の下敷きになるという事故によって、彼女はその生を終えた。
しかし、何故か意識は永遠に途切れることはなかった。再び目を覚ます頃には、見知らぬ天井、見知らぬ人、見知らぬ国、世界、景色、そして、自分の身体が彼女を迎えた。
それまでいた世界とは全く違う場所にいた。しかも身体は幼くなっていた。自分の手を見る限り、大体3才くらいであろうか。
目の前にいる男女の大人2人は、彼女を見て微笑んでいた。
意味不明な言語を喋りながら、ずっとニコニコしている。
普通の人間なら自分の身に何が起こったのかと焦る所だが、彼女は冷静に観察し、情報を集めることを優先した。
その末に得た結論は、『小黒友里』に転生したのである。