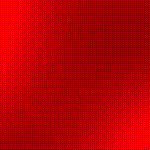幸い敵は鈍足らしく、敵影は無かった。
もしかしたら身を潜め、どこからか狙撃をしようとしていない限りは、まだ安全な地だった。
友里はフライアの肩に立ち、辺りを確認した。
戦闘を行うとすれば、ここの広さは十分であり、また閉演時間を超えているため、人は少ない。
職員はいるだろうが、少し離れたところに事務所があり、直接的な被害は考えづらい。
迎え撃つならここである。
下で人間の胴体ぐらいの太さの腕に抱きかかえられている奏汰を見下ろし、最後の忠告を彼に下した。
「奏汰、本当に逃げて欲しいの…………」
「お願いだ。そばに居させてくれ。どうしても、1人にさせておけない。それにさ、もう巻き込まれちゃってるんだし、最期まで付き合う」
彼の声のトーンは、普段のふざけている少年のものでも、友里の研究に呆れている幼馴染のものでもなかった。1人の男として、友里のそばにいると言っているのだった。
「……………分かった」
最終的に折れたのは友里だった。
「なあ、こいつを囮として使うのはダメなのか?」
「フライア(この子)は、まだ完全にセットアップしたわけじゃないの。逃げたりはできるけど本格的な攻撃が出来るわけじゃない。私がそばにいてあげないと……………」
「どれくらいで終わりそう?」
「あと20分。間に合わない」
「それなら、作戦を立てよう。時間を稼ぐんだ」
奏汰は口頭で、友里に焦り気味に、でも丁寧に自身が立てた作戦を一通り説明した。
「作戦は分かった。無理は、しないで」
「お前も、危なくなったら逃げろよ」
2人は作戦に出た。敵が来るまであまり時間はない。
木と木の間を通り、遊歩道を無視し、小さい子向けの遊具を跨いで坂を上って行った。
奏汰は必死に、園内を風にも追いつくほどの速さで走った。
向かった先は園内施設のレストラン。
公園内でも見晴らしのいい高い場所にあるこのレストランは、日中であればお昼ご飯やティータイムで賑わう、陽気なお食事処だが、闇夜では不気味さをはなっって静かに光り輝く街を見つめている。
奏汰は、その建物の室外機に足をかけ、屋根に上った。
高いな所にあるため、公園内の様子だけでなく、街の方もよく見えた。
目を細め、耳を澄ませると、先程友里の家の横にいた車が一台と、ロボット。
彼らの到着を見計らって奏汰は彼らが車から降り、武装した状態で園内へ侵入したのを確認すると、急いで屋根から降りて、用意してあった大きな石で窓を割った。
店内はしんと静かであり、人間がいてもおかしくはないような雰囲気であった。
奏汰は中に入ると、ずかずかと奥へと入っていき、店内のトイレの近くの赤いランプの前で立ち止まった。
「あった………。はぁ。不良になった気分だ」
ためらいながらも、覚悟を決め、その下の黒いボタンを強く押した。
ボタンが奥に押し込まれた瞬間、非常ベルのけたたましい音が店内に鳴り響いた。
音はレストランから漏れ、人気のない自然公園内では余計にその音が鳴り響いた。
奏汰は次の場所へ向かう前に、厨房に入り込み、包丁を一挺握り、外へ出た。
走る。走る。全力で走る。
さすがのアンドレの武装員たちもこの音には気が付いたようで、レストランの方に気を取られていた。
その隙に奏汰は駆け、レストラン近くにある建造物に向かった。
この前の工場爆発事件でも彼らは夜を狙い、今回も夜に友里の家を襲撃してきた。やっている事自体はそれなりに大がかりであるが、人目を嫌ってか、毎回夜に、しかも武装部隊、車、ロボットまでもが黒い。誰かにその姿を発見されることを彼らは望んでいないのだ。
非常ベルで事を公にし、運が良ければ彼らは逃げてくれる。例え逃げずに友里を探しに動いたとしても、この騒ぎを解消しなければ、彼らにとっても不利になり得る。そうして時間を稼ぎ、友里が攻撃するまでの時間を稼ぐ。
そう奏汰は考え、この作戦を提案したのだ。
次の建物、湖に面した休憩所がある。出井入り口は照明を落とした自動販売機が佇んでおり、木製のベンチは休憩所の中にひっそりと身を潜めている。
ここも憩いの場として日中は活躍し、子供たちはここでアイスを食べたりジュースを飲み、老人たちはこの場でお喋りをしているが、夜となった今ではこの場はレストラン方面から聞こえてくる警報以外は、静かである。
奏汰は、両手で抱える大きさの、凹凸の激しい石でガラス張りの窓を割って中に入った。
砂埃が床を覆っており、ザラザラとした感触が足から伝わり、またレストランと違ってこちらの方がずっと暗いので、より不気味で居心地が悪かった。
そこにもある、赤いランプ。またもや、その下にあるボタンを奥までしっかりと押した。
心臓が大きく跳ねるほど大きなベルの音。正常に非常ベルが作動してくれたのを確認し、すぐさま次の場所へと、建物を抜けた。
友里の部屋から脱出した奏汰は靴を履いていない。
靴下のまま石の上を走り、ガラスの上の歩いてしまったため、血が滲んでいる。
それでも走る。
彼は走る。
そして例のロボットの影が近づいていることに気が付かなかった。
「………!」
3本指のマニピュレーターが、彼の胴体を掴んでしまった。
機械に掴まれては、人間の、しかもたかが高校生である彼ではそれを引きはがすことは困難に等しかった。
そのロボットの頭部のセンサーの赤いランプが彼の顔を見つめている。
「この!離せ!」
無駄を承知で身体をくねらせて、どうにか逃げられないかと抵抗し続ける。
そんな事をすれば、マニピュレーターの出力を上げて身体が締め付けられるというのに。
「ああ!ぐっ!うぅ………」
外で友里の捜索をしている仲間に、無線で「早く殺す」ように指示を受けたのか、またはこの少年を痛めつけることに飽きたのか、肩から重機関銃を出し、銃身を彼の頭に向けた。
「ダメええええええ!」
聞き覚えのある女の子の声と共に、大きな影が奏汰を握るロボットの腕を掴んだ。
と同時に体当たりをしたため、その反動でロボットは腕を引きちぎられ胴体はズシンッと重たい音を立てて地面に倒れた。
ロボットの代わりに目の前に居たのはI-903。腕を完全に握り潰された、3本指のマニピュレーターは奏汰を離した。
フライアは地面に落ちないように、もう片方の手をお皿の形にして、奏汰の足場にさせた。
「友里!準備出来たのか!?」
「もう少しかかる!乗って!」
友里の声が目の前のロボットからしたかと思うと、フライアの出っ張った胸元の上部ハッチが開いた。
どうやた此処がこのロボットの操縦室らしく、奏汰がよじ登ると、開いたハッチがあり、中は外で見るよりも広かった。梯子があり、中に入って降りるとハッチが水平にスライドして閉じ、薄暗くなった。
奏汰は内部を見渡してみる。中央に設置された座席には友里が座っており、両手でレバーを握っている。前面の下にはノートパソコンぐらいの画面、真正面と左右には大きなスクリーンが壁のように張られており、外の状況が分かる。
頭上には、双眼鏡のような機器が細いアームで天井と繋がられている。
車の前座席ほどの大きさである操縦席だが、スイッチ類が多くあるため、2人乗るには狭く感じ、実際に奏汰は友里の後ろでしがみつかなければいけなかった。
モニター、おそらくはフライアの頭部のカメラアイが捉えたものを映しているのだろうが、敵のロボットが片腕がなくなった部位から火花を散らせながら、起き上がった。
「掴まってて!」
「掴まってろったって、ここしか………ああ!もう知らない!」
とっさに奏汰は友里の肩を掴んだ。
「きゃ!どこ触ってるの!」
「仕方ないだろ狭いんだから!」
身体をいきなり触られた友里は驚き、足元のペダルを踏み、両手に握るレバーを思いっきり引いた。
フライアは急加速し、後退した。
下部に設置されたモニターには残り3分と表示されている。
「セットアップ完了まであと3分。なんとか時間を稼ぐから、それまで逃げるつもり………!」
しかし、そんな暇を与えるほど敵のロボットが優しいはずもなく、その巨体の影が急に目の前に現れたかと思うと、さっきのお返しと言わんばかりに体当たりしてきた。
反動でフライアの足元は崩れ、軽い丘になっている公園の斜面を転がった。
「うわああああ!」
「きゃああああ!」
グルグルと何度も上下が逆さまになる操縦室の中で、2人揃って悲鳴をあげた。
ガコンッガコンッと地面が装甲にぶつかる音が、響いた。
下の方まで転がって、ようやく回転が止まったかと思えば、目の前には黒いロボットが立っており、片手でフライアの腕を掴み上げた。
相当の重量があるはずだが、フライアの身体は宙に浮いていた。
敵のロボットは、プシュウゥゥゥとエンジンから水蒸気を吐き出し、出来るだけ遠くへと投げ飛ばした。
地面にめり込む形となったフライアは、外にいる歩兵部隊に銃弾の雨を浴びせられた。
とはいえ、持ち前の装甲は見た目よりも頑丈であり自動小銃程度では傷はつかない。
手榴弾を投げた者もいたが、しかし、効果は十分ではなかった。
「友里、何か反撃出来る武器とかないのか!?」
「まだセットアップが完了してないから…………。」
敵のロボットが距離を取り、先程のように翼を展開して見せた。
「やばい!またミサイル撃つ気だ!友里!」
「分かってる!」
レバーを引くと、フライアは身構える姿勢を取った。
ここでまた、奏汰は考えついた。
「ミサイル撃ってきたら、敵の歩兵部隊のそばに行くってのはどうだ?同士討ちになってくれるかもしれないし、それに」
と奏汰が言ったところで友里は彼の言いたいことを理解し、ミサイルの発射を見計らってペダルを目一杯踏んだ。
フライアはまた急加速し、ミサイルとつかず離れずの距離を保ちながら、歩兵部隊にあえて突っ込んだ。
ミサイルは後を追い、しかも一発だけではなく数発なので、白い尾が木と木の間を川の字を描いた。
自分たちへ向かって、巨大なロボットとそれに釣られたミサイルが突っ込んでいると認識した彼らは、銃を向けながら後ずさりした。目標から視線を反らさないまま退避する行動。
やはり訓練された集団なのだろう。しかしさすがの彼らも、迫りくる死の前にはすぐに混乱し始めた。ある者は武器を捨てて逃げ出し、またある者は地面に伏せた。
結局は全弾が木に着弾し、爆発してしまった。
木を折り、地面を抉り、惨状とまではいかないにしても、ひと昔前の戦争の跡のようになってしまった。所々に火災がある。
歩兵部隊は、今の爆風で吹き飛ばされ、負傷したものが多くいた。
奏汰と友里にとって、これは好都合だった。同士討ちをしてくれたのだから。
黒いロボットの方も、ミサイルは全段撃ち尽くしてしまったようで、骨だけになった翼のように、背中のミサイル発射装置を展開したままである。
彼らの作戦失敗は目に見えており、奏汰も友里も内心「早く撤退して欲しいな」と思っていた。
しかし、2人の願いも虚しく、敵のロボットはまだやる気のようで、横に車輪を動かして回避行動を取りながら機銃を掃射している。
それと同時に下部のモニターには「セットアップ完了」の文字が表示された。
「友里!」
「うん!これで使える!」
友里は、頭上で吊るされたゴーグルを手に取ると、眼もとに持ってきて覗き込んだ。
外部では、フライアの背中から黄色く光る細かい粒子が無数に放出されている。
その一つ一つはただの粒である。
しかし、空中で粒子と粒子が結合されていき、一つのパーツが形作られる。パーツは何個も作られ、形がどれも違っている。すべてのパーツが合体し、一つの物体になっていく。それは、スコープの付いた、黄緑色の大型の銃器であった。
フライアは軽々と、自身の身長の約半分の大きさの銃を両手で構えた。
「これって………」
その光景を目の当たりにした奏汰はゴクンっと唾を飲んだ。
「対艦長距離連装粒子砲(ラグナロク)……………フライア(この子)の主砲だよ」
「主砲!?」
「そう。どんな敵も一撃で破壊するための威力を誇る、最強の武器。………そして、私が造った、最低の兵器だよ」
覗きながら、操縦席の右側に新たに出現したレバーを友里は掴んだが、彼女の手は震えていた。
彼女は、本来、好んで人を殺すような性格ではない。
彼女が殺すことを嫌うのは、人間に対してだけではない。どんな小さな動物も、虫ですら殺すことをためらい、ラボにクモが出てきた時には奏汰に追い出すように頼んだものだ。
殺さないように、というお願いを添えて。
彼女は、如何なる殺戮も看過できない。
しかも、それは小黒友里という少女としてでなく、ヴァ―レ・リーベと呼ばれた前世であっても同様だった。
彼女も恐れているのだ。その武器を使う事を。
彼女がその一度目の人生をかけて作り上げたその兵器の威力を。
それでも今この場で使おうとしているのは、彼女自身と、そして古谷奏汰という幼馴染を救うためなのである。
近くで彼女の苦悩を目の当たりにした奏汰はその時、何にも言えなくなってしまったが、全てが終わったらゆっくり話そうと決意し、レバーを握る彼女の手に自身の手を重ねた。
彼女の緊張と熱が、手を通じて伝わってくる。薄っすらと汗がにじみ出ている。
彼女がゴーグルで覗く景色は、ゴッデシュ・シュラーグと名付けられた銃のスコープ型のカメラが移したものである。
フライアは完全に敵のロボットを捉えており、銃を発砲する用意も出来ていた。
友里は心臓がそわそわするのを何とか抑えて、深く息を吐いて指を引き金にかけた。
この一発で全部終わる、そう信じて。
そしてついに敵のロボットが向きを変えようと一度止まる直前で、引き金を引いた。