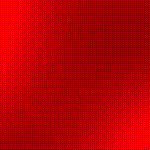フライアが隠れる森から奏汰は1時間ほど走って、ようやく家に着いた。
夕飯も朝ごはんも食べず、しかも起きてそう時間が経っていないものだから、奏汰の視界はグニャリと曲がり、息が切れ、心臓がドキドキと脈打ち、汗で身体が濡れている。
膝にとついて息を整えて、やっとのことで顔を上げると、そこにあったのは奏汰の家と、大きな穴が開いて「KEEP OUT」と黒字で書かれた黄色いテープが何重にもなって張られた友里の家である。
パトカーが数台、家の前に停まっており、その他警察車両らしき特殊な車も並んでいた。
警官も複数人おり、バタバタと右から左、左から右へと駆けまわっている。
何かメモをとっている者もおり、時折仲間から何かしらの報告を受けている。
奏汰が、家に近づくと、警官らしき人が腕を彼の前に出した。
「ここから先は危ないので入らないで。立ち入り禁止だよ」
奏汰が顔を上げると、その警官は背が高く40歳ぐらいで、色黒だった。
皺が出来ており、顔は大きいが、頬のところはくぼんで見えた。
微笑んでいるわけではないし、怒った顔でもない、感情の読めない表情だった。
「あの、俺、ここの家のです。古谷奏汰って言います」
おずおずと自分の名前を出してみると、警官は何かを報告するために肩につけられたトランシーバーに手をかけた。
「あ、あの」
「奏汰ッ!!」
奏汰が言いかけたところで、警官の後ろから母親の声がした。
奏汰の母親は真っすぐと彼のもとへ走って来た。
今にも泣きそうな顔であった。
警官の脇を抜けて奏汰の前までくると、もう離さないと言わんばかりの力で彼の身体を抱きしめた。
「か、母さん…………」
奏汰はあまり突然のことでびっくりしていたが、やがて状況を飲み込むと腕を彼女の背中へ回し、抱き返した。
「どこ行ってたの!もう!」
その扱いは小学生や中学生へするのと同じであった。
母親にとって、息子というものはいつまでも経っても自分の子供なのである。
それは、幼稚園生や小学生はもちろん、中学生、高校生になっても、そして大人になったとしても同じものである。
ましてや、自分の息子がよく遊びに行く隣の家の壁が、原因不明で大きく崩れ、しかも遊びに行った息子が一晩中連絡つかず行方不明となっていたら、親はどれほど心配するだろうか。
「確認しますが、息子さんで間違いないですね?」
先ほどの警官が、今度は優しく微笑んで訊ねた。
「はい。うちの息子です」
半泣きになりながら、奏汰の母親は答えた。
「いやあ、良かった良かった」と言いながら、その人は再び、無線で何かを報告している。
「おい、一体、どこ行ってたんだ?心配したんだぞ」
母親に抱きしめられていて気が付かなかったが、奏汰の父親も、すぐそばに立っていたらしい。
「父さん…………ただいま。……………ごめんなさい。母さんも」
まずは連絡もなしに家に帰らなかったことを2人に謝った。
すると「いいのよ」と母親は優しい微笑みを浮かべながら、奏汰からゆっくりと離れると、 すぐに真剣な面立ちで彼を見つめた。
父親は余計な言葉述べず、妻の息子を静かに見守った。
「あのね、大事な話があるの」
重しい口調でそう告げた。奏汰の母親が彼に伝えたいこと。それは奏汰の中では分かっていた。
「驚かないで聞いて……………すごく辛いことかもしれないけど」と母親は続ける。
「お隣に住む友里ちゃんがね…………………遺体で見つかったの」
「それじゃあ、君は何も知らないんだね?」
灰色のスーツに、水色のネクタイをつけた坊主頭の男性が奏汰にそう確認した。
奏汰は今、警察署に設けられた取調室でお茶の入ったコップを片手に、刑事と対面で椅子に座っている。
家に帰り、母親から友里が亡くなったという事実を打ち明けられた後、事情聴取を行いたいという警察からの要請により、奏汰たち家族はそれに応じた。
部屋の中には非常に質素で、白い机と簡素な椅子、ノートパソコン以外に、物と言えるものはなかった。
刑事の後ろにももう1人、壁に向かって腰かける警察官の姿もあり、どうやら記録しているらしい。
目の前にいる刑事は優しそうで、ニコニコしながら、でも真剣な眼差しで、d系るだけ怯えさせないように配慮しながら、奏汰から情報を聞き出そうとしている。
昨日、どこでどのようにしていたのか、亡くなった小黒友里について知っているかなど、実に様々なことを質問してきた。
それもそのはずだ。奏汰の幼馴染である友里の家の壁が破壊されいていて、しかも友里と奏汰は共に行方不明、挙句の果てに数キロ離れた自然公園にて友里の遺体が発見されたのだから。
しかし実際は、奏汰も多くの事を知らない。ただ、なんだか狂暴な凶悪犯にでもなったような気持ちになった。
アンドレという組織に襲われたらしかったが、しかし、実のところはとく分からない。なんで友里が狙われたのかも、どうして昨日それが行われたのかも。だからただ、淡々と昨日、彼が自分の目で見て、身体で感じたことを話した。
「はい。ただ、誰か分からない人たちが友里の家に来てて、皆、武器とか持ってたんです。それで友里と俺は走って逃げて、でも、その途中ではぐれてしまって」
奏汰は出来るだけ本当のことを言うように努めた。ただし、友里が元科学者であったこと、また、フライアの事などは、警察に知られるとまずいので、これらは伏せて説明した。 そのためいくつか矛盾するような説明になってしまいそうになったが、なんとかその場を乗り切ることが出来た。
彼自身、嘘をつくことは得意ではないし、真実を離さないことに対して引け目もあった。仕方のないこととはいえ、彼の目の前に座っている刑事にも申し訳ないことをしていると、彼の心は沈みに沈んだ。
「分かった。それじゃあ、今日はここまでだから、かえって大丈夫だよ。また後日よろしくね」
「はい、失礼します」
一礼して、奏汰は部屋を出た。
そのまま埃の匂いがする廊下を歩き、刑事に入り口まで見送られた。
警察署の出入り口を抜けて車道に出ると、奏汰は一度振り向いた。
奏汰はそれから、誰もいない公園まで歩くと、辺りを見回してからペンダントを取り出した。
「やっと終わった?」
ペンダントを出した途端、青い部分が点滅し、突然フライアの声がした。
「うわ、本当に通信できるんだな……………。気持ち悪っ」と奏汰は呟いた。
「聞こえてるからねー?」
わざと大き目の声でフライアが反応した。
「分かった。分かったから、もうちょい声を落としてくれ」
「もう、繊細なんだから、女の子にもっと優しくしなきゃだめだよ?」
「俺は誰に何を教わっているんだ」
はぁ、と軽いため息をつき、ペンダントを掴みながら、奏汰は空を仰いだ。
「それで?これからどうする気なの?」
フライアの声は奏汰に問いかけた。
「とりあえずフライアにはそこにいて欲しい。他の人に見つからないようにしてくれ」
「うん」
「……やけに素直だな?」
「操縦者がいなければ、私に出来ることは限られているから。今人間に見つかったら、私にとっても都合が悪いの」
「それじゃあ、俺を操縦者として認めてくれ」
「それは嫌」
きっぱりと断ってきたフライアに、奏汰は半分呆れ気味に目と目の間をつまんだ。
友里が託してくれたものだから、フライアを無碍に扱うことは出来ない。しかし、ここまで訊き訳が悪いとさすがにイライラしてしまう。奏汰は、ただの高校生の男子である。成人し、心身ともに成熟した大人というわけではないので、仕方のないことだ。
「分かった。じゃあ、俺がお前の操縦者として認めてもらえるように頑張るからさ。見ててくれよ。見えるんだろ?」
「お前じゃないよ。フ・ラ・イ・ア!」と抗議してから、フライアは答えた。「もちろん見えてるよ。そのペンダントにはカメラが付いているから、貴方の周りにあるものの映像が随時私のデータベースに転送されてくるもの」
フライアは俺のことを「お前」って呼ぶんだな。奏汰は思ったが、指摘したところでどうにもならないような気がし、心の中でツッこむ程度に留めた。
「俺は、しばらくはそっちに行けない。さすがに学校とかあるし、怪しまれる。それに………」奏汰は俯いた。「まだ、心が追いついていないからさ」
ペンダントは青く光ってはいたが、声はしなかった。