翌朝、窓から太陽の日が差し込み、電線やら電柱やらの影が徐々に伸びてきた。
奏汰が目を覚ますと、頬に乾いた感覚。
身体を起こして、そっと頬を触ってみるが、何も無い。
「朝、か」
昨日は夕飯を食べていないし、お風呂にも入っていない。そのまま眠りこんでしまったのだ。
はっきりとしない頭のまま、ベッドから降りて、自室から廊下に出た。さすがにずっと同じ下着にYシャツは不快感があるので、奏汰はとりあえずシャワーを浴びることにした。
下に降りると、母親はもう起きており、みそ汁を作っていた。
「あら、おはよう」
「おはよう」
軽い挨拶をかわし、奏汰は脱衣所へと歩いた。そこで衣類を全て脱ぎ、浴室内へと入った。シャワーノズルから勢いよく飛び出す無数をお湯の線。
お湯が床に叩きつかれる音を聞きながら、ボディーソープやらシャンプーやらを付け、泡立て、身体の汚れを洗い流す。数年ぶりとなる朝のシャワー。お湯の温かみと少し開いた窓から流れてくる外気の涼しい風が心地よい。
タオルで濡れた身体をふき取り、洗ってある下着とYシャツを着ると、身支度を整えた。
「ほら、お味噌汁だけでも飲んでいきなさい」
脱衣所からあがり、居間に来た奏汰に、母親はみそ汁の入った茶色いお椀を渡した。
「ああ、うん。ありがとう」
今の壁に掛けられた少し古い時計を見れば、すでに針は8:15をさしている。
悠長に朝ごはんを食べている時間はないのだ。
「やば。もうこんな時間か」
「奏汰、まだ、無理して学校に行かなくてもいいのよ?」
心配そうな表情で、優しい声色を使ってそう提案する母だが、奏汰は「大丈夫」と短く答えて、熱いみそ汁を一気に喉に流し込んだ。
奏汰は「ごちそうさま!」と慌ただしく茶碗をテーブルに置いて、学校用のリュックを背負った。
玄関へと走り、外へ飛び出そうとした、その時。
「私も連れて行ってーーー!!!!!」
上の階から、少女の叫ぶ声が聞こえた。
「あら?今の声何かしら?」
謎の叫び声を聞きつけた母親が、階段を登ろうとした。
「な、何でもないよ!あー…とそうだ!ちょっと忘れ物しちゃった!」
「もう、気をつけなさい?」
奏汰は母親つ掴めるように両腕を出してそう言うと、クルッと向きを変えて階段をかけ下がった。
声の主は分かっている。自室に入り、机の上に置いてあるペンダントを拾い上げた。
「何のつもり!?見つかったらどうするんの!?」
下にいる母親に気が付かれないように声を潜めながら、顔を近づけて問い詰めた。
「だって、ここで大人しくしているなんて嫌だもの。ここじゃ暇。貴方、昨日ずっと私のペンダントを置きっぱなしにしていったでしょ。さすがにそれは無いと思うよ?」
「だからって……あぁもういいや。とにかく学校には持って行けないぞ」
「これは貴方にとっても重要なことなんだよ?」と今度は深刻なことのように、声のトーンを落とした。
「私のパートナーとして相応しいかどうか確かめる。そのためにも、ペンダントを持って行って欲しいの」
「いやでも、ペンダントを学校に持ってくなんて……………」
奏汰が口ごもると、ペンダントから大きく息を吸う音がした。
口などあるはずもないことは誰にでも分かりきっていることだが、フライアが何を主張しているかを考えれば、彼女がこれからしようとしていることを考えるのは想像に難くない。それは奏汰にとっても同じことだった。
「ちょっとそれヤバいから!ここで叫んだら聞こえちゃうから!」思わず奏汰はペンダントを両手で覆った。「分かった分かった!」
仕方がない、と諦めて、時間もなかったものだから、とりあえず首にペンダントをかけて爆竹が轟くよかのうに階段を駆け下りると、家を飛び出した。
外は快晴。悲しいぐらいに晴れである。流れる雲など、一つも存在しない。太陽が1つ、地上にあるあらゆるものギラギラと見つめ、焦がしていく。
はぁ、はぁ、と息切れさせながら、奏汰はアスファルトの上を走っていく。
歩いていくには少し時間がかかるものだが、男子高校生の体力は伊達ではなく、遅刻しまいとする焦りから、信じられないほど早く走って何とかギリギリ間に合った。
学校の下駄箱で下履きから上履きに履き替えてからも、固い床を走る。上履きの底は薄いから、衝撃がもろに脚に伝わる。正直言って、今の彼にはしんどいものだった。
ガラガラと、ドアを開けるとクラスメイト達はすでに教室に集まっており、ガヤガヤと、友達同士でお喋りしている。
「お!来たか。おはよう、奏汰」
登校したばかりの息切れした奏汰に話しかけたのは、やっぱり友樹であった。
「あぁ、おはよう…………」
恐らくは気を利かせて、友樹はいつもの調子で奏汰と接そうと努めているが、奏汰の方は中々その気に慣れなかった。どこか陰気な雰囲気を漂わせており、他者を近づけることは良しとしないというような、そんな気さえしてくる。
もちろん意識してそうしているわけでは無い。彼自身、大事な友人の厚意を無下にすることは本意ではない。
無意識に奏汰は胸元のペンダントを握りしめた。
「奏汰………それって」
友樹の視線が奏汰の胸元に移った。しまったと奏汰は思った。この高校では、おそらく他の大抵の学校でもそうだろうが、余計な装飾品を身に着けてきてはいけないのが校則として乗っているものだ。学校という制服に青いペンダントを首から下げていれば目立ちもする。そのため、余計な茶々を入れる者がいる。
クラスにいる健司がそれだった。
「おはよう!奏汰!」と2人の横から割り込んできた彼は奏汰のペンダントを掴んで顔に近づけた。「これは何?もしかして小黒の形見的な?」
少し小ばかにするような声で、健司は周りの生徒に聞こえるように言った。クラスメイトの視線が奏汰に降り注いだ。
奏汰はその視線が嫌で、また彼のこのどうしようもない性癖に呆れ、俯いて、健司の手を払い除けた。
「健司には関係ないだろ」
ぶっきらぼうに奏汰は言った。
「関係ないねぇ……………。一応、小黒の葬式に行って”あげた”んだけど?」
厚かましさを感じさせる彼のこの言動は、クラスメイトを不快にさせた。教室内の雰囲気がどんどんと悪くなっていく。
お前なんか、来なくてよかったのに!と奏汰は心で思いながらも、それを口に出すことはなく、ただ睨むことしか出来なかった。
2人は口を開かない。沈黙。その数秒間にわたる沈黙を破ったのは、黒板側の出井入り口の戸がガラガラと開く音だった。
「はい席につけー」佐藤先生はいつもの口癖のように言って教壇に立つと、奏汰と健司の2人が睨み合っているのが目に入った。
やれやれ、と呆れ気味にため息をつきつつ「ほら、そこの2人もさっさと座りなさい」と注意をする。
注意された奏汰と健司は互いに睨みあっていた目を反らし、自分の席へと向かった。途中、奏汰は一度振り向き、健司の方を睨んだが、それ以上のことをすることはなかった。
他の生徒たちも、席に着き、それぞれの荷物を机にしまいこみ、授業の準備をしつつ1日の連絡事項を伝える先生の声に耳を傾けていた。
その後、教室内の雰囲気は悪かった。
今日だけではない。
ここ2、3日ほどはこの状態である。それもそのはずだ。まだ出会って数か月も経たないとはいえ、クラスメイトが1人、亡くなってしまったのだから。教室にいる1人ひとりの居心地の悪さや、どうにもやりきれないという感情が生んだこの空気はどうやっても払うことは出来ない。少なくとも、いまこの時ばかりは。しかしながら、そんな感情や空気に支配されないものいた。山宮健司という男だけは違った。
彼は他とはまったく別の性質をもっており、いまの奏汰を茶化すほどに、人間性に難がある少年だった。今朝方あったように、奏汰のペンダントが友里からのものであると知りながら、それでもネタにして笑おうとした。
これにはクラスメイトも、もちろん奏汰や友樹も呆れ果てている。
とはいえ、奏汰の方はもう彼を恨んでいない。今は、学校の授業を聞きながら、時折ポケットに仕舞ったペンダントを手で軽く握っていた。
1日の授業が終わり、ホームルームでさよならの挨拶を済ますと、また健司に絡まれないように、早歩きで教室を出て行った。
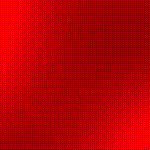


![[エルシャダイ]ネット流行語大賞の注目ゲームがお披露目](http://www.magical-shop.net/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/static/thumbs/12.jpg)



