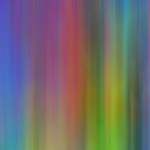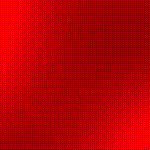「旅立つなら、明日がいい」とハンザは言って、白いコップに入ったお茶を一口啜った。
お別れに最後の夕飯をとった僕らは、大きな窓のそばにある、紫色のソファーに腰かけてゆっくりしている。
外はもうすっかり暗くなっていて、水色の月の光が夜空に浮かぶ雲を照らし出していた。
今まで気が付かなかったけど、この世界の月は地球で見た月よりもずっと大きく、模様がはっきりと見える。
もしかしたらこの地上に月が落ちてくるんじゃないかと、錯覚を覚えくらいに。
そんな月を横目にみながら、僕もカップに手を添えて、お茶を一口啜り、背の低いテーブルに置いた。
食道や胃の中に熱いものが流れるのを感じた。
「じゃ今日は寝て、明日の朝にでも旅立つことにするよ」
「今日はうちで泊まっていってよ。最後になるんだしさ」
「分かった。そうする」
自動食器洗い機が水を噴射する音以外は何も聞こえないほど、部屋の中は静かだった。
僕とハンザの二人だけである。
イオはイシカの部屋へ行ったらしく、今はここにはいない。
「昔は、もっと平和だったんだ」
ハンザは月を見ながら、呟いた。
「あいつらもその時は大人しくて、問題を起こすようなことはなかったのに……」
僕は黙って聞いていた。
気まずくなったのか、ハンザは突然立ち上がった。
「外の空気を吸いに行こう。今日は風も穏やかだしさ」
ここの風はいつも穏やかだと思った。
「慶介は、イオのことどう思ってる?」
「え?」僕にはハンザの言っていることが分からなかった。
「ただの家族?妹みたいなもの?」
「家族……だよ?」
「ふーん。ま、それならそれで良いんだけどな」
「急にどうしたの?」
「なんというか、イオは凄いよね。強くてさ。イシカや俺の母さんから教わった料理もすぐに覚えたって聞いたよ」
え?いつのまに?
「なぁ、慶介。イオのこと大事にしなよ。俺が言うのもなんだけどさ、これからの旅、イオが慶介を助ける機会はたくさんあると思うからさ」とハンザは続ける。
「異世界に旅をしに行くっていうのは、危険を伴うものなんだ。決められた安全な航路、安全は方法なんてものはどこにもない。俺だって、君たちがいなかったら野垂れ死んでいたかもしれない。イオや、もちろんコスモスも、慶介を助けるために必死になるだろうさ」
それは分かってる。
「いや、分かっていない」
僕の心を見透かしたかのようにハンザが言う。
気が付けば、彼は僕に向き直っていて、僕の目を優しく笑って、でも真面目な表情で見つめていた。
「いつか、イオにもコスモスにもどうしようもない問題がきっと起きる。君でなければ解決できないような問題が。そんなとき、2人を守ってやらないとね」
僕には、何のことかさっぱり分からなかった。
ただ、いつまでも僕が守られてばかりではいけない。2人を守れるような人にならなければいけないと、そう強く思った。
涼しげのある風が優しく頬をなで、周辺の草を揺らした。
その音は、聞き心地の良い歌の様だった。
朝になって、僕とイオは身支度を整え、コスモスの客車の乗降口のところに立った。
「もう行くんだよな」
「うん」
「また、来てよ。今度はもっと歓迎するからさ」
「もちろん」
僕とハンザは数秒の間、お互いの目を見つめあった。
「それじゃあ」
僕はハンザに背を向けて、乗降口から降ろされた梯子に手を掴み、足をかけた。
車内は僕とイオ以外はいなかった。
「コスモス、発車して」
「かしこまりました。発車します」
汽笛が鳴った。どこか寂しげな響きだった。
列車はガタンッと音を立てて走り出した。発車して間もなく、車輪は地面から大きくはなれ、まるで空中を滑るように走っていった。
「大丈夫ですか、マスター?」
「うん。僕は大丈夫だよ」
やっと出来た異世界の友達なのに、こんなにも早く別れが来るなんて思っても
見なかった。
僕はあの世界の土地が、風が、人が好きだった。
ハンザ……イシカ……。
指揮所内のキャプテンシートに深く座り、肘掛にもたれてため息をついた。
「ご主人様、お茶です」
「ん。ありがとう」
お盆を抱えながら、温かいお茶の入ったコップを渡してくれた。
それを飲んで昨日のことを思い出していた。
押し殺していたはずなのに、どうしようもない寂しさが再び僕の心を蝕んだ。。
まだ、あそこに居たいと思った。
でも、そういう訳にはいかない。
ハンザの言っていた通り、彼らには彼らの問題があり、同じようにこっちにもこっちの問題がある。
双方、お互いに関わり合いすぎることは出来ない。
部外者は関わるべきじゃない。
少なくとも僕はそう思ってる。
「これで、良かったのかな………」
正直、かなり迷いはあった。
メインモニターに映し出された空の映像は青々としていて、この空の下で暮らすことも出来たかもしれない。そう思った。
「マスター、正体不明の通信を受信しました」
突然のコスモスの報告に、僕は悩むことを中断して繋ぐように指示した。
「かしこまりました」と返事をし、外の景色を映し出していたメインモニターが、どこか建物の屋上のような風景に切り替えられた。
そこには覚えのある男の姿があった。
彼は特別総合防衛会社SAMAELの社長、マルム・ミューゼック。
コスモスとイオを引き渡すように要求してきた張本人。
「やあ、慶介君、先日はどうも」
「あ、どうも」
ニヤリと不敵な笑みを浮かべる彼に、軽い口調で返した。
「何か御用ですか?」
昨日のことがあり、正直かなり嫌悪感を抱いている。
出来れば顔を見ずにさっさと切ってしまいたい。
「なに、少し君と取引したい。単刀直入にいうと、やはり我々は君のその船が欲しいのだよ」
指揮所内の空気が、一気に重いものになる。
「お断りすると、言ったはずですよ」
「まぁまぁ、今日は少し趣向を変えてみた。交換するのは君の好きなモノではない」
「どういう意味です?」
「今回交換するのは君の大事な大事な『お友達』だ」
彼はそう言うと、後ろにあるものをこちらに見せるように身を引いた。
「……!!」
僕は信じられない光景に目を疑った。
画面に映し出されたのは、ハンザ、イシカ、そしてハンザの両親が手を後ろに拘束された状態で、銃を突きつけられている映像だった。
「君がその船を渡してくれれば、彼らには傷ひとつつけないでおいてやろう」
「人の………人の命を何だと思っているんですか!?」
「吠えるなよ。部下がうっかり引き金を引いてしまうかもしれないだろう?大丈夫だ。君が大人しくその列車を渡してくれれば、銃を突きつけるのをやめ、拘束を解き、無事に解放してあげよう」
「…………その人たちに、その人たちに手を出さないでください。お願いします」
僕は出来るだけ深く頭を下げた。
「それはお前次第だ。お前のせいで可哀そうな家族の頭が吹っ飛ぶのなんて嫌だろう?我々をあまくみるなよ。お前がハンザという少年を助け、お礼に数日泊めて貰っているのは調査済みだ。友達、なんだろう?嫌だよね、友達を失うのなんて」
マルムはねっとりとした声で言った。
どこまで腐っているんだ!
僕は今までにないほど憤慨していた。
力強く拳を握っていて、爪が食い込んだ。
許せない。友達をあんな目に合わせるあいつらも、巻き込んでしまった自分も。
こうなる可能性だって考えられたはずなのに……!!!
マルムの酷く醜悪な顔がアップで映る。
「期限は今から5時間後だ。指定場所はデータで送った。その時間までに戻らなかった場合、一人ずつ射殺する」
そこで通信は終了し、メインモニターは再び外の景色に戻った。
「そんな……」
10秒ほどこの指揮所は沈黙に包まれた。
「ご命令を、マスター」と沈黙を破ったのはコスモスだった。
僕は考えた。一生懸命に考えた。思考を巡らせた。
ハンザ達を助けたい。
でも、それはコスモスの譲渡を意味する。
コスモスを守りたい。
でも、それはハンザ達を見捨てることになる。
素直に渡したところで確実に助かるという保証もない。
もし、もしもの話だけど、渡した後に僕ら含めて殺されたら元も子もない。
じゃあ、コスモスに砲撃してもらう?ミサイルとか機関砲とか撃ってもらう?
でもそれじゃあハンザ達も危ない。
イオに対人戦を仕掛けて貰ってもさすがに人質が4人に敵は武器を持った奴らが数名以上だし、そもそもイオの身体能力が知られてるなら何かしら対策されてるとみていい。
僕は考えた。結論を出せないまま。
「わ、私、助けたいです。ハンザさんたちを」
「イオ……」
今まで黙っていた彼女が口を開いた。
「理由は分からないんです。…………でも、ここであの人たちを見捨てたらきっと、後悔する。そんな気がするです。私は今できることをやりたいです」
はっきりと僕の目を見つめてそう言った。
そこには彼女の強い意志があり、いつも僕に従うだけの、彼らが言うような『人形』ではなく、一人の人間としての姿を見た。
その瞬間、なんだか頭の中にあった大きくて固い岩が崩れたような、今までせき止められていた川の水が再び流れ出したような、そんな感じがした。
何を迷っていたんだろう僕は。
ハンザ達を見捨ててはいけない。もちろんコスモスも渡してはいけない。
どちらもかけがえのないものなのだ。
イオと目線を合わせる。
2人でうなずき、僕は覚悟を決めた。
メインモニターに視線を移す。
「コスモス、反転して。今から作戦を立てよう」
「了解しました!!」
「了解しました!!」
やってやる。必ず助けるから。
だから、待ってて。
日が傾き始めている。
今日は一年の中でも最も日が沈むのが早い日だ。
俺は遠くの方で豪壮に構える山々を置いていくように飛ぶ白い鳥たちを見つめた。
足には疲労が溜まり、喉はカラカラに乾いている。
「お兄ちゃん…………」
隣でイシカの不安で一杯な声がした。
俺たちは今、母さんも父さんも含めて拘束されている。
ついさっきと違って銃を突きつけられているわけではないけど。
こんなことをするように命令したどっかの誰かさんは呑気に簡易の屋外用のソファーに腰かけ、テーブルには飲み物が置いてあった。
服装は紫を基調として、噂通り悪趣味な社長さんだ。
コスモスが飛び立ったあとに、武装集団が僕の家に突撃してきて何が何だか分からないまま拘束され、ここに連れてこられた。
先ほどの浮遊していたアイボールカメラと連中の会話から察するに、俺らはコスモスを強奪するための人質らしい。
「してやられたな」
小声でそう呟いた。
本当に、どこまで腐ってるんだ。
彼らの性根の腐ったところには怒りを越えて憐れみを感じるところまで来ている。
「私たち、どうなっちゃうんだろうね」と隣にいるイシカは弱々しい声を上げた。
周りで銃を構える兵士たちに聞こえないように小さな声で答えた。
「さぁね。どうなるんだか、俺にもさっぱり分からないや」
「慶介さんたち、もうとっくに他の世界に着いてたかな。逃げて、くれたかな。…………助けに、来てくれないのかな」
「ずっと言っているでしょ。これは俺たちの問題。そもそも慶介は何も悪いことしてないんだからさ。俺たちに構ってないで、逃げてくれた方がいい」
そう、これでいいんだ。
これで………いいんだ。
……………よく、ないよな。
せめてイシカだけでも、どうにかして逃がす方法はないかと思索する。
まずは拘束。
これは加工された鉄か何かで作られているのかとても重いし、固い。
どうにかして壊す、なんて手段は現状ない。
くそ…………この時点で詰んでるな。
諦めにも近いものを感じ、空をもう一度眺めようと視線を上げたその時、俺らを射殺するであろう銃を持った男の一人が黒いマスクを外して、もう一人に聞いた。
「本当に、この家族を殺すのか。この家族、何もしていていないんだろ。何時間も立たされて可哀そうに」
「上からの命令だ。仕方ない。ま、上があんなのだと先が思いやられるがな」
こいつらは、何も知らない………?
そうか、下っ端には教える必要がない、そういう事か。
「し、聞こえるぞ」
3人目の男が会話に加わった。
「俺たちをこんなことに使うなんてな」最初の男が言う。
「感情は不要だ。ただ与えられた任務をこなせばいい」と3人目。
「そう、俺たちはただの戦闘員。気にすることはないさ」と2人目
「そうは言っても、俺にはあの子たちぐらいの娘がいるんだ。できれば、こんなことはしたくないんだがな」
「じゃあ、お前は命令を放棄するのか?そしたら俺がお前の心臓に鉛玉ぶち込んでやる」
2人目の男が左手の人差し指を最初の男の胸をつつく。
男は黙り込んでしまった。
もうちょっと頑張ってくれないかなぁ……。
でも、これで少し分かったのは、彼らもまたあの社長の被害者だってこと。
そういえば、この会社の悪い噂がたったのはあの社長は就任してからだな。
「もうすぐ時間です」
「ああ、分かった。ご苦労」
「はっ!」
特別総合防衛会社SAMAELの社長、マルムは立ち会がり俺たちの方へ歩み寄った。
「君のお友達が助けに来てくれるといいな」とそいつは俺たちに笑いかけた。
反吐が出そうなほど、嫌な顔と声だった。
「慶介は来ないさ。さっさと諦めて解放してほしいんだけど?」
「可愛くないガキだ。なぁ、そう思うよな」と今度はイシカに視線を向ける。
イシカはそっぽを向き、知らんふりをした。
「今射殺してやってもいんだぞ?そういう趣味はないが……………将来は美人になっていたかもしれないのに可哀そうにな?」
奴はイシカの太もものあたりに手をまわし、撫でまわした。
「ひっ」とイシカは小さく悲鳴を漏らした。
「俺の妹に触るな!!」
拘束されていることも忘れて叫んだ。
次の瞬間、パチンッと乾いた音がして右頬に鋭い痛みが加わった。
マルムが無言で俺の頬を叩いたのだ。
そして何でもなさそうに、ただこげ茶のハンカチを取り出し、俺を叩いた手の甲を拭いた。
「お願いします、息子たちだけは見逃してください!!」と母さん。
「だめだ。あの少年と繋がりが強い」
「あんた達は私たちを守ってくれるんじゃないのか!?」父さんは怒鳴った。
「その守るためにはあの強力な船が必要なんだ。あんな子供が持つべきではない」
それは暴論だ。
今時、俺らぐらいの年になれば異世界へ行くのは普通だし、武装をしていたっておかしくはない。コスモスはたまたまその性能がこの世界の技術より優れていたってだけで……。
そんな風に思っていると、何の前触れもなく聞き覚えのある音がした。
この辺りじゃ滅多に聞かない、いや、この世界では聞くことはもうないであろう汽笛の音。
あれは間違いない………。
「社長!!」
部下の一人が空を指さした。
「来たか」
「嘘だろ……。なんで……」
太陽を背に、こちらに向けて走って来る細長い影。
それは何度も見た覚えのあるもの。
友達の大切な家族。
なんでだよ。なんで来たんだよ。慶介………。
コスモスは建物の屋上に停車した。
そして茶色い箱のようなものに貼り付けられたような扉が開いた。