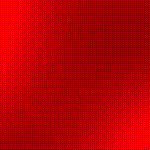フライアは奏汰が首から下げる青いペンダントに備え付けられたカメラを通して、彼女のパートナーである古谷奏汰を見ていた。
奏汰は目の前にいるロボットに、わざわざ物を投げつけて、自分に注意が向くように仕向けている。
何故か。それはロボットの足元にある。
逃げ遅れた人間2人がロボットのそばにおり、危険な状態なのである。
フライアにとっては、ただの人間が2人。しかし奏汰にとっては違っているようだった。
ただの人間が2人いるのではなく、人が2人もいるのである。もっとも、ロボットの脅威に晒される人が、1人でも2人でも、彼は同じことをしたであろうが。
フライアは自身に搭載されたAIをフル活動させて、今までの情報を処理している。膨大なデータである。それは小黒友里の人生の記憶と、彼女の死後、奏汰が見せた行動の全てについてだった。
小黒友里の隣にいつもいる彼は、子供っぽくも、感情が豊かであり、文句をいいながらも彼女を気遣い、実験やら研究やらに付き合っていた。また、他の人間から蔑まれたり、不当な扱いを受けないよう、彼女を庇う事もしていた。
奏汰の優しさは今も変わらない。困っている人間がいれば、すぐに行動に移して助けていた。それは落とし物をしてしまった人が、落とし物を探すの手伝うという小さなことから、敵わないと分かっていながらも、逃げ遅れた人を助けるために、ロボット相手に石を投げて誘導しようよする彼の姿を。
フライアたち戦闘用ロボットにとっては1人の脆くて弱い、ただの人間。彼女たち兵器に簡単に殺されてしまうような存在。
彼の行動は明らかに無謀だった。ロボット相手に生身の人間がどうにか出来るはずがない。本人も、そのことは熟知しているはずである。現に、彼の心拍数は上昇しており、表情からは恐怖が垣間見える。それでも、身を挺して赤の他人を助けようとしている。死ぬと分かっていてもなお、彼の行動は変わらない。いつだって、誰かを助けるのである。
人間は、よく分からない。彼女は思った。何故、個体を助けるために、自らを危険に晒すのだろうか。自分だけ逃げて、助かる道を選択すればいいものを。
本当に、分からない。
フライアは記憶を辿る。これまでに似た事象がないか、小黒友里の記憶を参照する。
彼女は生前、自身が作りだした発明品で、奏汰同様、困っている人を助けていた。時々失敗もあったようだが、それでも彼女は「ありがとう」と笑顔で言われることに、幸福感を感じていたようだった。それは自身が目標を達成したことによる満足というよりかは、むしろ誰かが幸せになったことを認識し、自身に感謝の言葉を述べられたことで満足していたようだ。
幸福?目標?感謝?
どれも、分からない。分からないことだらけだ。ひたすら短い時間で、この膨大な情報量をフライアは思考する。
私には、感情がない。あくまで、プログラムで感情があるように見せているだけ。
彼女はもう一度、ペンダントの向こうで他人を助けようとする奏汰の姿を見つめる。彼女の生みの親が愛した人物。そして自分のパートナー。
フライアは、決断をした。
用水路でずぶ濡れになりながらも、溝に自身のガッシリとした身体を隠して、奏汰は額に汗を浮かべながらロボットを見つめていた。
靴には水が浸水し、シャツも服もべったりと肌にくっついている。
横風が一瞬、ふわっと吹くと、ロボットはズシンッ、ズシンッとゆっくりと近づいてきた。
奏汰の脳裏には自分の死が過った。手に、背中に、額に、厭な汗がどっと流れる。胸がざわつく。死にたくない。死にたくない!死の恐怖が彼を襲った。彼にとって人の死とは何よりも孤独で、計り知れない闇を纏っている。
友里はその闇に飲まれた。
でも、彼はこうも考えた。このまま、出来るだけ誰かが逃げる時間稼げれば、それでいい。もしもこのまま死んだとしても、あの世で友里に会えるかもしれない、と。
ふと、目を閉じてみる。友里の姿を想像してみる。水色の髪を降ろしている後ろ姿。ダボダボな白衣は、いつも彼女が着ていたトレードマークだ。友里は振り向いた。奏汰に、彼女は柔らかく、朗らかな笑みを浮かべる。奏汰は心の中で、今から死んでそっちに行くと伝える。途端に、友里は顔を真っ青にし、次には目に涙を浮かべて怒っている。そしてこう叫ぶのだ。
「奏汰は諦めないで!」
奏汰は、小さく笑みを浮かべた。彼には想像できてしまうのだ。奏汰の死を拒む、小黒友里という少女の姿が。ずっと、隣にいたから。小黒友里ならば、奏汰の死を望みはしないだろう。彼には判る。ずっと、そばにいたから。もしも、悪夢でも見て、友里が奏汰にむけて「こっちに来て……」などと言えば、彼は一発でそれが偽物の友里だという事に気が付くだろう。それくらい、彼には自信があった。
「厭になるよな。本当に……」
自分勝手だよな、と奏汰はつぶやく。小黒友里とはそういう少女だったのだ。自分を顧みず、他人の不幸をよしとしない。助けられるものは助ける。
奏汰は瞼を開け、ロボットを睨む。
どうにかして、敵の注意を引きつつ、自分が助かる道をさがさなくちゃ。
行動を起こそうと身構えた、ちょうどその時だった。彼が首から下げている、青いペンダントが点滅し、軽快な少女の声がした。フライアだ。
「奏汰!!」
「ふ、フライア?!」
「ペンダントにキスをして!それで、私の名前を呼んで!」
フライアからの思いもよらない指示に、奏汰は目を丸くする。
「ばっ!?こんな時に何を言ってんだ?!」
「お願い。奏汰」
今度はトーンを落とした声。
あ……、と奏汰は気づいた。
名前。フライアが彼の名前を呼ぶことはこれが初めてだった。
「お願い、信じて。奏汰」
フライアの声のトーンはいつものような明るさではなく、真面目そのものだった。本物だった。少女のAIを搭載したロボットとしての声ではなく、強い意思を持った女性の意思表示。人間的な力強さを感じ取った。
「……分かった」
奏汰は胸元のペンダントを掴み、口付けをした。その姿が、友里のあの日の動作と被って見えた。
天に向けて、ペンダントを掲げる。
「来い!フライア!」
その瞬間、大地は揺れ、コンクリートで舗装された道路がひび割れ、奏汰の目の前に大きな影が姿を現した。白い土埃が舞い、煙幕のように辺りを白い煙が包む。煙の中で黒い影は立ち上がった。
とっさに奏汰は前のめりになって、両腕を顔の前で構えて顔を守った。目を細く開き、目の前の影を見た。
「あ……」
そこに居た。
土埃が風で流され、視界が晴れていった。
鎧のように装甲を重ねた、屈強な脚。脚は曲線を描いており、角度によってはスカートに見えなくもない。その割には比較細い腰だったが、肩にはこれまた鎧兜のような装甲が取り付けられている。砂時計のようなフォルムをとるロボット。
思考人型機動戦車………タイプI-903………フライア………!!!
彼女はそのまま、ロボットと奏汰の間に割って入った。
「……んなのありかよ……」
ペンダントを空に向けたまま、奏汰は呟いた。けれど、あいつが作ったロボットなら、これくらいやって当然か、と自分を納得させて、フライアに近づいた。目の前に現れた脅威を認識した敵ロボットは、極太な腕を彼らに向け直した。腕の一部がハッチのように開き、再びミサイルが発射され、白い尾を引いて真っすぐに向かってきた。
「うわあああああ!!!」
奏汰は驚いて叫び、目を瞑って両腕で顔を覆った。同時にフライアは奏汰を守るように、彼の身体を両腕で包んだ。
ミサイルがフライアに着弾する直前、青い五角形の板が無数に張り付けられたような、半透明のドームが展開された。ミサイルはその壁にぶつかり、爆発したが、その内部にいるフライアたちは無傷だった。
そっと奏汰が目を開いたが、彼はまだ自分が生きていることを実感した。
「あ、れ、ミサイルは……?」
「攻撃型防御障壁(ミョルニル)で防いだから大丈夫。早く乗って」
フライアは胸元のハッチを開けながら、彼に手を伸ばした。奏汰は彼女の機械的な腕に乗ると、ハッチからコックピットに身を投じた。
ハッチを閉めると一瞬暗くなったが、照明をフライアが点けたことで内部構造が分かった。中には以前乗った時と同じように、座席があり、真正面にはモニター、左右にレバーがあった。
奏汰は座り、両手でレバーを握る。
「攻撃の照準は私がやるから、奏汰は身体の操作をお願い」
「操作たって、俺動かし方知らないんだけど!?」
「足元のペダルが全身と後進、レバーは上半身だよ」
「そんなこと言ったって……」
「来るよ!」
モニターに目をやると、フライアのメインカメラがとらえた外の景色が映し出されており、敵ロボットがこちらに歩み寄ってきているのが分かった。
しょうがないか、と軽く息をつき、奏汰はキリッと顔を引き締めた。
「行くぞ!」
「うん!」
力を込めて、足元にあるペダルを踏んだ。
フライアはその操作に合わせて脚を一歩、また一歩と敵と同じようにゆっくりと歩き始めた。