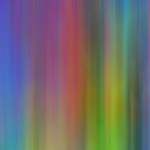いつもの森へとフライアは奏汰を乗せてやってきた。辺りはすっかり薄暗くなった。大きな物音を立てない様に注意しながら、足を踏み入れる。
「ここまで来れれば、ひとまずは大丈夫かな」
奏汰はようやく落ち着けるな、とまた背もたれにもたれかかった。フライアのコックピット内は1人分というには、少し広く思えた。
前は、友里がここに座ってたんだな。
外の様子を映し出すモニターを眺めながら、奏汰は口を開いた。
「フライア。助けてくれて、ありがとうな」
彼女は静かにその言葉を聴いていた。こういう時、どう返せばいいか分からなくて、ただ黙っていた。
その様子を奏汰は優しい表情で見つめ、小さな子供に語り掛けるようにして、こう訊ねた。
「なぁ。なんで、突然、俺をパートナーって認めてくれたんだ?」
「それは……」
実のところ、彼をパートナーとして認めたフライア自身も、決定的な理由があったとは言えない。奏汰が自分の身を犠牲にして、誰かを守ろうとした姿勢に感銘を受けただとか、弱くても立ち向かおうとしていた姿が恰好よかったとか、無理やり理由を並べ立てることも出来たが、そうしなかった。フライアは、当たり障りのない返答をした。
「奏汰が、悪い人間じゃないって分かったから」
「ふーん。そうか」
奏汰はただ両手を枕にして、天井を眺めた。
「奏汰、これからどうするの?色々な人間に、私の姿見られちゃったけど……」
ここに来るまでにどうにか人の目を抜けて来ることが出来た。しかし、あのような騒ぎが起きて、大勢に彼女の姿を目撃されてしまっては、おそらく捜索されるだろう。そうなれば、見つかるのも時間の問題だ。2人はこれからどうするか、改めて考える必要があった。
「んー。どうしようかね」
気の抜けた声で返事をしつつ、あれこれ考えて見る。しかし、今の彼は完全に疲れ切っている。とてもこれからの事を考えるような体力はない。
「ま、そこはおいおい考えるさ。取り合えず、今はさ、お疲れ様、フライア」
「そんな呑気なこと言っていられないと思うよ?これから先、多分、向こうも本気でくるんじゃないかな」
「それは、友里の記憶から考えたこと?」
そう、フライアには友里の記憶と人格がインプットされていると、本人が言ったのだ。今の発言も、おそらくは友里の記憶を辿って導いた考えなのだろう。
「そう。それに、たった1人の転生者を殺しにくるような連中だよ?私によってロボットが2体も破壊されたんだから、明らかに危険視するようになると思うのが普通だと思う」
「確かにな」
めんどくせー。と奏汰は頭をかく。彼女の言う通り、呑気にしていられない状況なのは事実だ。どうするかを決めなくてはいけない。奏汰はスマホを取り出し、メッセージアプリで、母親に友達の家でお泊りをする旨を伝えた。
「とりあえず、今日は一緒にいるよ。その方が、お互い安心だろ?」
「男女が森で2人きり……何も起きないはずがなく……」
「起きねぇよ!」
すかさずツッコむ奏汰に、フライアはかすかに笑った。
なんでAIがそんなボケをかましてくるんだ……。
少々呆れ気味に奏汰はそう思う。
「奏汰は、またロボットが出てきたら戦うの?」
ふと、そんな質問をフライアは投げかけた。
突然のことに一瞬、奏汰は考えるように視線を下げたが、またモニターの方を見た。
「そのロボットが暴れて、誰かが傷つくなら、俺は止めたい。フライア、協力してくれるか?」
「分かった。奏汰に協力する」
「ありがとうな」
「もう、寝た方がいいよ。人間は、睡眠が必要だから」
「早くね?」と言おうとした奏汰だったが、確かに、疲労感自体はあり、またこうして座席に座っていることもあり、もう眠るのもありだなと考えるようになった。結局、うつらうつらとして、眠りに落ちてしまうとフライアはコックピット内の照明を消した。
翌日、朝に奏汰は自分の家に帰った。母親からは先日の一件もあり、心配されたが、自身は大丈夫であることをアピールした。夕食を抜いてしまったので、朝ごはんをいつもより多めに食べた。大盛りのご飯をかき込む奏汰の姿を、母親は心配そうに見つめた。
奏汰は「ごちそうさま!」と言ってリビングを去ると、今度は自分の部屋へと駆け上がった。もちろん、その間も例のペンダントは身に着けたままである。
部屋の中は少し散らかっており、つま先立ちで床を渡ると、収納棚から箱を取り出した。その箱は以前、友里が渡したものだった。
「これだ」
つい最近、つまりは友里が生前、自信ありげに奏汰に見せた「プロテクター」だ。
「これだね。製作者様(小黒友里)が渡したプロテクターっていうのは」
ペンダントが点滅し、フライアの声がした。
「ペンダントをそのプロテクターの胸元に近づけて」
「こう?」
「そそ」
奏汰がプロテクターを上部を持ち上げると、胸当てのところに自身が首から下げるペンダントを近づけた。
ペンダントは青白い光を照射し、プロテクターの白い表面を照らす。
「うん。間違いないよ。このプロテクター、私の規格に合わせてあるね。製作者様(小黒友里)の記憶からしても、これは、奏汰を守るために作られたものだよ」
「あいつが……。でも、あいつ、俺のことは巻き込みたくないって……」
「それは……」
「こうなること、見越してたのかもな……」
寂しそうな奏汰の瞳と声に、フライアは黙った。外に吹く風は窓をガタガタと揺らしていたが、それも止んだ。部屋に沈黙が流れる。
「よっし、他の物も運ぶか」
奏汰は自分を元気づけるように声を張ると、立ち上がって、プロテクターの上半身を大き目のリュックに詰めた。さすがに上下を一緒には入りきらなかったので、残りはもう一つバッグを用意してそっちに下半身用のプロテクターを入れた。奏汰はリュックを背負い、バッグを持つと、階下へと降りて行った。母親にバレないようにつま先で歩き、音を立てなかった。しかしながら不運にも、ちょうど母親が台所から出てきてしまった。
「あら、どうしたの?そんな荷物もって?」
「あ、えっと。これは、ちょっと山にでも行こうかなって。友達に誘われてさ」
嘘下手くそか!
自分で自分にツッコむも、どうにか切り抜けられないかと母親の方を見る。彼女は、エプロン姿のまま、真顔でしばらく奏汰を見つめている。それから、奏汰の母親は彼の方へと歩くと、玄関に置いてあった虫除けスプレーを渡した。
「虫さされ、持って行きな」
笑顔になり、母親はそう一言、優しく言った。
「あ、うん。ありがとう」
素直にそれを受け取って、奏汰は自転車に鍵を手に、玄関を出た。
籠にバッグを入れ、自転車を漕ぎ出した。
「お母さん、優しい(?)んだね」
揺れるペンダントから、今まで黙っていたフライアが話しかけた。
「何で疑問形なんだよ……」
「私には、人間の感情っていうのがいまいち分からないから。優しさとか、愛情だとか、悲しみも、分からないから」
淡々というフライアの声。それは彼女が機械で出来た存在だということを思い出させた。
「……そのうち分かるようになるんじゃねぇの?ほら、漫画とかじゃよくあるじゃんか」
「私、マンガ、知らない。」
ギラギラと照らす日差しの中、奏汰は汗をかきながら自転車を漕いでいた。
小さな信号に掴まり、停車していると突然、声をかけられた。
「奏汰!」
声の方を振り向く。そこに立っているのは、長身の男子。よく慣れ親しんだ顔。友樹だ。
「友樹……」
ハッと奏汰は思い出した。
昨日のロボット騒ぎで、友樹が巻き込まれたんじゃないか。それが心配で走りだしたというのに、一番肝心なことを、ロボットとの闘いで忘れていたなんて。
友樹は顔に絆創膏、腕には所々、傷やら痣がある。どれも、奏汰の家に訪れるまでは無かったものだ。まさか、あの場にいたのだろうか。
「や、やぁ。お前、昨日のロボット騒ぎ………」
「お前、ロボットに乗って戦っただろ?」
奏汰の声に友樹がかぶせた。
あ……。
やっぱり、あの場に居たんだ。良かった。生きていてくれて。怪我はしているようだけど、今こうして目の前に立ってくれている。申し訳なさと、安堵の気持ちにボーっとする奏汰に、友樹は近づいた。
「お前が、あの緑のロボットを動かしていたのか!?あれはお前のロボットなのか!?」
「え、あ、うん」
物凄い剣幕の友樹に、奏汰は思わず肯定してしまった。
まずい!この事が他者にバレるのは!
「な、なあ……」
友樹は拳を握り、頭を垂れる。それからバッと顔を上げ、さらに奏汰に近づいた。
「凄いな!」
「……………………へ?」
なんとも間抜けな声が奏汰から漏れ、とっくに青になっていた信号は再び赤く光った。