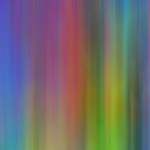「つまり、あのロボットは小黒が造ったもので、お前が操縦者になった、と?」
「まぁ、そういうこと」
フライアのいる森へ続く道を、奏汰は自転車を押して、友樹はその横を歩いて行く。
奏汰は結局、フライアのことを友樹に打ち明けた。さすがに、小黒友里の人格と記憶をAIにインプットしていることは隠したが、小黒友里は転生者であること、彼女がフライアを造ったこと、フライアが自律して思考出来ること、戦闘用であること、今は森に隠れていることは順を追って説明した。
友樹は奏汰よりも漫画やアニメが好きで、特にロボットモノに大いにはまっていたのだった。さすがに友樹に話したのはまずかったかなとも考える奏汰だったが、味方がフライアしかいない現状、相談相手が欲しかったのだ。彼も、精神的には疲れていた。そんな苦悩を知ってか知らずか、友樹はフライアの場所へ連れて行ってくれとお願いして、今にいたる。
「そのペンダントが、キーなんだな?」
友樹は奏汰が首から下げた青いペンダントを指さした。
「まぁ、そんな感じだな」
「そうか。確かに、小黒の形見っていえば、形見だな」
「あぁ……」
ゆっくり、ゆっくりと眺める景色を眺めながら奏汰は会話を続けた。
「でも、まさか、あそこにお前がいたなんてな」
「逃げ遅れた子がいてな。ロボットモノは好きだが、人が、ましてやあんな小さな女の子が目の前で殺されるのを黙って見ていられなかった」
あの時、泣き叫ぶ女の子を抱きしめて守っていたのは友樹だったのだ。
つくづく、優しい奴ばかり周りにいるもんだな、と奏汰は思った。
「本当に、お前が無事でよかったよ」
「奏汰と、えっとフライアだっけ、お前らが頑張って倒してくれたおかげだよ。知ってたか?俺の周りの逃げ遅れたやつら、お前たちを応援してたんだぜ?」
「え?」
「だってそうだろ?街で暴れるロボットを止めるもう一体のロボット。何も知らないやつからみれば、ヒーローだ。そう、ロボットモノによくある展開だ」
「はぁ……」
漫画は奏汰も読む方ではあるが、ロボットモノの話は全く分からなかった。
そうこう話しているうちに2人は街を抜け、裏道の坂を下ると森へと入って行った。
しばらく木と木のトンネルを抜けて、河原に辿り着いた。2人がいる位置は橋からは死角になるため、見つかる心配がない。
「フライア、出てきてくれ」
奏汰の声に反応して、ズシンッズシンッとう足音が木の影から大きな人型が出てきた。
「おぉ!」
友樹は興奮気味に目の前に立つフライアを見上げた。
「意外と小さいな」
「開口一番が小さいって酷くない?!」
呆れた声でフライアが言う。
「うおっ!?喋るのか、ビックリした」
「自分で考えて行動できるって言っただろ。このAI、会話も出来るんだよ」
奏汰の解説に何故かエッヘンと腰に手を当てて得意げな姿勢になるフライア。
「なるほどな。でもさ、それなら何で搭乗者が必要なんだろうな」
「たしかに」
それは考えたことが無かった。
友樹は、興味津々といった様子で、フライアの足回りを腰を屈めて観察した。
「………奏汰、この人気持ち悪い」
「なっ、気持ち悪いって言われた?!」
「友樹はロボットモノが好きでさ。フライア見て喜んでるんだよ」
フライアはメインカメラのレンズを調節し、友樹の顔にピントを合わせた。
「相澤友樹。奏汰の親友だね。製造者様にもかなり親切にしてたみたいだし、奏汰ほどじゃないけど好感は持ってたみたいだね」
「製造者様って友里のことだよな?俺のこと知ってるのか?」
「私には製造者様である小黒友里の記憶と人格がインプットされているからね」
「そうなの!?」
悪気もなく奏汰が言わなかったことをフライアは平然と述べる。「しまった!」と思った奏汰だったが、彼女には一切友樹には内緒にしてくれ、など言っていなかったため、責めることが出来なかった。それよりも友樹の興奮の方が高まってしまった。
「小黒はそんなことまでしてたのか!どんだけ天才なんだよ…………。っているか奏汰、そのこと隠してたな!」
耳元で叫ばれ、奏汰は耳を手で押さえた。
「説明が面倒になるとでも思ったんだろ?…………まぁ、確かに、驚き尽くしでこっちも理解が追いつかないけどな」
友樹はフライアに向き直った。
「でも、お前とフライアは俺たち普通の人間を救ってくれたんだ。ありがとう、2人とも」
今までの興奮に満ちた感情はどこへ行ったのか、笑みは優しいものへと変わり、声のトーンも落ち着いていた。「ありがとう」その言葉を一文字一文字を噛み締めるように、大事にしてに述べたのだ。
彼の眼差しは、尊敬の念が含まれていた。
「さて、フライア。このプロテクターをコックピットに入れさせてくれ」
「分かった」
フライアはコックピットのハッチを水平に開き、片手を地面につけた。その手に奏汰はリュックを背負い、バッグを抱えて乗った。
「あ!待った!俺も乗るぜ!」
「お前内装みたいだけだろ」
「バレた?」
「そりゃ………。てかフライアは知らない奴はコックピットに入れるの嫌がるぞ。俺も最初拒否られたんだからな」
フライアは奏汰を持ち上げ、奏汰はコックピットに乗り移った。
「そうなの?あ、女子の部屋に勝手に入っちゃいけないみたいなもんか」
「お、分かってるじゃん」
「だろ?」
2人の会話に奏汰は何故かモヤモヤした感情を抱いた。微妙に友樹とフライアの意気投合しているような気がしたのだ。
「まぁ、奏汰の友達だし、別にいいよ。見るぐらいなら」
「やりー!」
再び、フライアは地面に片手を置き、友樹のために足場を作ってやった。
リフトのように彼を持ち上げると、胸元のコックピットのハッチの周りに乗せた。
その間、奏汰はコックピット内に入り、座席の後ろにリュックやらバッグやらを置いた。
「ほへ~。こんな風になってんだな。ザ・SFって感じだな。割とシンプルか?いやでも機器もそれなりにあるな」
ハッチの縁に手を突き、中を見渡しながらブツブツ見渡してる。
「中、結構広いんだな」
「2人入るとさすがに狭いけどな」
奏汰は自分の作業を進めた。
「奏汰、コックピット内には収納がそれなりあるから、その中に荷物入れて。じゃないと戦闘中、リュックとかバッグが散乱しちゃうと思うから」
「おっけ」
リュックとバッグからプロテクターを取り出すと、さっそく座席の斜め後ろに収納用の蓋を開けて中にしまいこんだ。
「なあ、やっぱ見た目よりもコックピット広くないか?」
ハッチから覗きながら、友樹が言う。
「そう?」
「だってこのサイズのロボットで、これだけ装甲が厚いのに、コックピットこれだけ広いなんて」
「まぁ、友里が造ったんだからこれくらい当然だろ」
「お前なぁ。すっかり小黒に影響されちゃって…………。いいか?この技術、もしもこの世界に公開されたりなんかしたら、フライアの価値が爆上がりして、解体されて研究されることになるかもしれないぜ?」
友樹のこの発言に奏汰は動かしていた手を止めた。
考えていなかったわけじゃなかった。オーバースペックのフライアが、世界中の注目を集めてしまう可能性。研究のために、没収されてしまう可能性を。小黒友里は死ぬ間際、「フライアをお願い」と言った。彼女が託してくれたものをそうやすやすと手渡すことは、彼にはできなかった。
「そんな事………」
「そんな事、私自身が許さないわ」
「え………?」「え………?」
奏汰が言おうとしたところでフライアが口を挟んだ。男子2人は彼女のこの言葉に、思わず間の抜けた声を漏らした。
「なんでか訊いていいかい?」
「製造者様(小黒友里)の記憶では、私のことを娘みたいに思ってくれていたみたいなの。同時に、絶対に世界に渡してはいけない、超危険な兵器としても見ていたみたいなの」
このことは確かに、友里本人からも言われたな、と奏汰はあの日の記憶を辿った。
「でも、小黒はお前を完成させた。誰かの手に渡ってはいけないのに」
友樹はコックピットの上部に座り、目の前に位置するフライアの顔、正確にはスクリーンに守られた大きな高性能カメラを見つめた。その映像は、コックピット内のパソコンぐらいの大きさのメインモニターに映しだされた。
「この世界には、まだ転生者がいる。製造者様(小黒友里)と同じように………。そいつらはこの地球を手に入れようとしている。対抗するには、絶対に私が必要だと考えた」
「いまどき世界征服ね。流行らないと思うけどな。漫画の世界じゃないんだから」
「でも、不可能じゃない。実際に、製造者様(小黒友里)が元いた世界では、異世界に侵攻して、征服することがあったと記録にある。この地球は技術力が圧倒的に低すぎる。彼らに制服されるのも時間の問題かもね」
「そんな奴らに、フライア一体で立ち向かえって?無理じゃないか?いくら最強といってもさ、限度があるだろ」
「ああ、それは俺も疑問に思ってた」
荷物をしまい終えた奏汰が、梯子を上ってハッチから顔を出した。
「私も、どうして製造者様(小黒友里)がそう考えたのかは分からない。私の機能では、彼らを掃討するような力は…………。もしかしたら、私に記憶と人格を移植したあとに、何か機能を取り付けたのかもしれないし、これだけで十分と考えたのかも………」
「「「んー」」」
3人は唸って考える。小黒友里という少女がどのような考えでフライアを完成させ、奏汰に託したのか。例の一件以来、分からないこと尽くめだ。
「小黒は何考えてたんだろうな。全部計算してのことか、それとも思いつきか」
「いやあいつ死ぬ間際に、フライアに俺を登録させたんだぞ。絶対何か考えてるって」
そういう奏汰の口調はいつもの調子で明るかったが、表情はどこか寂しそうなであった。その一瞬の変化を友樹は見逃さなかった。
「そんな事してたのか………」と友樹は答えつつ、立ち上がった。
「買い出し、頼まれてるの忘れてたわ。俺はそろそろ戻る」
「あ、じゃあ送ってく」
「いいよ。お前はフライアのそばにいてやりな。まだまだ、2人で楽しいお話があるでしょ。すまん、降ろしてくれ」
フライアは胸元に手を置き、友樹が乗り移るのを確認する、地面へと降ろしてやった。小石がビッシリ詰められた河原を踏むと、友樹は後ろを向いて手を振った。
「じゃあな2人とも!今日はありがとうな!奏汰、明後日学校こいよ!出来たらでいいからさ!」
奏汰とフライアは手を振り返した。
「やっぱり、いい友達だね」
「……あぁ」
2人は小さくなる友樹の後ろ姿を見届けた。