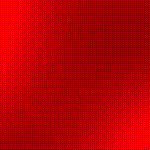月曜日。スマホのアラームがなる5分前、奏汰は目を覚ました。夢から現実世界へと引き戻された彼は、ふと、友樹に「明後日、学校に来いよ!出来たらでいいから!」と言われたことを思い出した。暗い部屋に遮光カーテンの隙間から漏れる日の光が、空気中に漂う埃を幻想的に輝かせる。彼の心の悲しみも、数日も経てばある程度は軽減した。とはいえ、今でも小黒友里の死について思い出すと吐き気を催してしまうが。それでも、悲惨な光景を思い浮かべさえしなければ、何とか持ち直すことができた。
ベッドを折りて、冷たいフローリングに足をつける。あまりよく眠れていなかったようで、頭はまだボーっとする。フワフワとした感覚のまま立ち上がると、一瞬ふらついた。
「おはよう。奏汰」
机に置いてあるペンダントは青白く点滅し、フライアの声がした。いい加減、この光景にも慣れたもんだな、と奏汰は思った。
「………おはよう」
素っ気なく返し、今日は学校へ行こう、と制服に着替え始めた。念のため、ペンダントの上には必要のない教科書を被せておいた。
高校の校則では夏季衣替え期間ということで、半袖のワイシャツを着て、薄手のズボンにベルト巻いて締めた。
ペンダントは一応持ち運びしておこうと先日、フライアと相談して決めた。ただし前みたいに、他のクラスメイトに絡まれるのは本意ではないため、ポケットにしまうという形になった。
階下へ降りると、奏汰の父親はもう出勤したようで玄関には靴が一足無かった。階段を下りて折り返し、台所の扉を開けると美味しそうな匂いが鼻を突いた。
母親は皿を洗っており、食卓には朝ごはんとみそ汁、サラダ、小魚と漬物が置いてあった。
「あら、おはよう。さっさと食べちゃって。私も今日町内会で早めに出たいから」
「あ、うん。…………いただきます」
未だに眠い頭のまま手を合わせてから、箸を右手で掴み、ご飯を口に頬張る。次に漬物を口に放り込み、シャキシャキとした触感と塩味を堪能してからまたご飯を食べる。今度はみそ汁を飲み、お腹に熱い液体が流れる感じがする。
「はい、お茶」
「ん」
母親は急須から緑茶を注ぎ、湯気の立つカップを奏汰の右に置いた。
小魚を数匹、箸でとりご飯と一緒に食べる。最後にお茶を飲むと「ご馳走様」とシンクにお皿を持って行き、玄関へと向かった。
「行ってきます」
トントン。靴を履いて、扉を開けた奏汰。
「行ってらっしゃい」
母親の見送る声を聞いてから、バタンッと閉めた。
隣の家を見てみる。もちろん友里の家の方だ。半壊した家は灰色のネットが覆われており、薄っすらと工事現場などでよくある足場が見えた。友里の家族は、もう住んでいない。例の一件の後、どこかへと引っ越してしまった。どこへ引っ越すのかいつ引っ越すのかというような話を聞いた気もするが、その時は、全てに対して虚無感しなく、また困惑も混じっていて奏汰はよく覚えていなかった。
彼女たち一家が住んでいた家は、おそらくは中に家具などは一切なく、建て直されるか、一度完全に解体されるかするだろう。奏汰が小さな頃から毎日のように遊んだあの家。友里が笑ったところを見たあの家。友里が泣いたところを見たあの家。友里と過ごしたあの家。友里が実験やら研究やらに耽ったあの家。友里が、友里が、友里が。2人が紡いだ思い出のつまる家は、あっけなくも壊されてしまった。彼にとって何よりも価値のあるあの家は、赤の他人からすれば、無価値の半壊した家としか映らない。
「行ってきます」
小声で呟いて、背を向ける。これから向かう学校へと歩み始めた。1人で歩く時には、大体イヤホンをつけているが、今回はそうしなかった。朝である今は、小鳥のさえずりの方が、彼の心を癒すのに十分だった。坂を登っていく。登りきる頃には、コンクリートの地面には蜃気楼が揺らいでいる。もうすぐ6月も終わり、本格的に夏となる。思えば、今年の梅雨は雨が少なかった気がするな。そんな事を考えながら、坂の下にある家のソーラーパネルを眺めた。まだ8時にもなっていないのに、降り注ぐ太陽は熱い。肌の表面にある細胞や皮膚のバリアーを焦がしている。
杉田高校の制服を着る生徒がちらほら見えるが、全員知らない顔。
「お!奏汰!」
でもなかったようだ。
明るい声は、2日前に聞いた声そのものだった。
「……おはよう。」
そう返す奏汰の肩に腕を回し、友樹は笑いかける。
「おう。おはようさん。やっと来てくれる気になったか」
「まだ1日しか休んでないぞ」
呆れ顔で奏汰は言うが、抵抗はしていない。
「そんなにくっついたら危ないよ?」
後ろからの声は花蓮のものだった。
「宮野さんもおはよう」
「うん、おはよう」
こうして、3人で登校することになった。
友樹はいつもの調子で奏汰に話しかけるが、花蓮はどこか気まずそうにしている。花蓮は奏汰の幼馴染である小黒友里が亡くなったことを気にかけているのだ。そしてフライアのことなど微塵もしらない。2日目、奏汰と友樹はフライアのことは男同士の約束ということにしたため、伝えられなかったのだ。だからなぜ友樹がこんなにも通常運転で話しかけられるのか、少々違和感を覚えていた。
奏汰も友里も、良い人だといことを花蓮は知っていた。しかし、彼女にとって最も人間関係に敏感なのは友樹なのだ。彼は常に明るく、ポジティブ思考であり、比較的豪快な要素も持ち合わせていながら、誰かへの気遣いは怠らない性格をしている。それは前に友里や奏汰を健司から庇ったことからも分かる。だからこそ、もう少し、奏汰に遠慮がちになってもおかしくはない、と彼女は考えた。或いは、普段通りに接することで精神的に負担をかけないようにしようという配慮なのかもしれない。いずれにせよ、人に気遣うことでは、友樹にはかなわないと、花蓮は思ったのである。
友樹は男同士の会話を止め、花蓮も話に入れるように話題を選択した。奏汰はそのことに気がついたが、指摘せず話を合わせた。いや、話に持ってかれたといった方が正確である。奏汰が自発的に会話しようと思ったからである。
学校に着くと、3人は教室へ入った。
教室の出入り口をくぐると、先に来ていたクラスメイトたちの視線が奏汰に向けられた。ビクッと一瞬だけ怯む奏汰だったが、友樹が「行くぞ」と小さく声をかけて先導した。花蓮は近くにいた女子たちにおはようの挨拶をして、壁になるように動いた。奏汰は奥へと進んだ。健司は、まだ来ていないようだった。
自分の席に座り、教科書やノートを机に入れる。布で出来た筆箱は空いた隙間にねじ込んだ。リュックは机のよこにおいた。
左隣りの席に目をやる。そこには、誰もいなかった。中は多分、空っぽだろう。友里は荷物は全部持って帰る方だったし、そもそも、持ってくる勉強道具が少なかった。
慌ただしい足音が廊下から響いて聞こえ、バンッとドアが開けられた。健司が予冷の時間ギリギリに登校してきたのだ。
「あぶねー。寝坊してきたわ」
「遅刻ギリギリじゃん」
彼は、リュックを床に置きながら前の席にいる男子生徒と笑いあっている。
「あれ、古谷君がいるじゃん!おはよう!」
友樹とは違った、厭らしい明るい声に奏汰は「おはよう」と素っ気なく返した。
あいつにだけは関わって欲しくないという奏汰の願いは簡単に壊された。
そのタイミングで佐藤先生が入ってきた。
「はい座れー。ホームルーム始めるぞー」
こうして、退屈な授業が始まった。